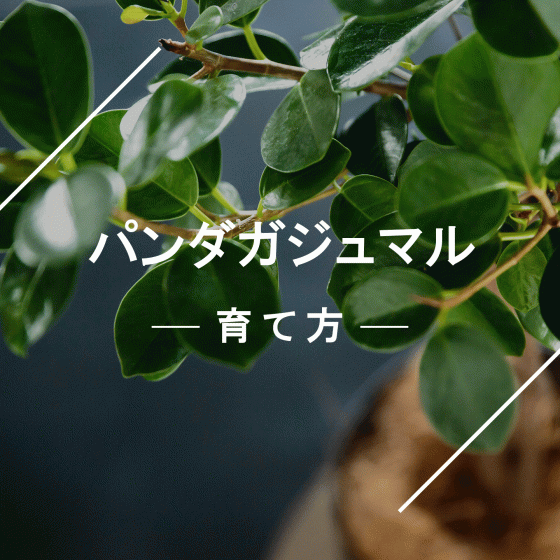キュウリの育て方
公開日 2025年03月18日
更新日 2025年04月22日
育てやすさ
育て方の難易度は普通レベルです。
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

キュウリの基本情報
| 植物名 | キュウリ |
| 学名 | Cucumis sativus |
| 和名 | 胡瓜 |
| 英名 | cucumber |
| 別名 | 唐瓜(カラウリ) |
| 原産地 | ヒマラヤ地域 |
| 科名 | ウリ科 |
| 属名 | キュウリ属 |
| 開花時期 | 6月~8月頃 |
キュウリは生で食べられることの多い夏野菜です。
食べると身体を冷やす効果があり、疲労回復の効果も期待できます。
比較的育てやすいものの、成長に合わせた手入れが必要です。
月別栽培カレンダー
種まき
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
植え付け・植え替え
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
肥料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
開花
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
種類と品種

キュウリの種類は収穫時期によって2つに分けられていて「冬春キュウリ」と「夏秋キュウリ」があります。
品種はさまざまなものがあり、それぞれの違いは耐病性や収穫量、品質の差です。
代表的な品種である白いぼキュウリ、いぼなしキュウリ、ピクルス用品種を解説します。
| 品種 | 大きさ(cm) | 甘味 | 味の濃さ | フルーティ | 酸味 | さっぱり感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白いぼキュウリ | 20〜40 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| いぼなしキュウリ | 17〜20 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◎ |
| ピクルス用品種 | 8 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◎ |
栄養成分と健康効果
キュウリは水分量が95%を超えていて100gあたり13kcalと低カロリーな野菜です。
キュウリの基本的な栄養成分と健康効果は、以下の通りです。
| 栄養成分 | 健康効果 |
|---|---|
| カリウム | 高血圧予防に効果的 |
| ビタミンK | 丈夫な骨作りに効果的 |
| ビタミンC | がんや動脈硬化予防、老化予防に効果的 |
| ビタミンA | 抗酸化作用があり、美肌効果がある |
| 不溶性食物繊維 | 便秘や下痢の予防、むくみ予防に効果的 |
旬の時期と味の違い
キュウリは品種改良や栽培方法の工夫によって一年中収穫ができますが、1番美味しくなるとされる旬の時期は6〜8月です。
旬の時期になるとみずみずしさが増し、パリっとした食感がとても良くなります。
キュウリの歴史と主な生産地
キュウリの歴史は古く、3000年前には原産地のヒマラヤ、インドやネパールで栽培されるようになり、中国を経て日本には6世紀の中頃に伝わります。
日本に伝わった当時のキュウリは苦くて普及しませんでしたが、江戸時代に品種改良されて全国各地で栽培されるようになりました。
現在の日本のキュウリの主な生産地は宮崎県、群馬県、埼玉県です。
キュウリの育て方
キュウリを上手く育てるためにいくつかのポイントを確認しましょう。
- 土壌の準備と場所選び
- 水やりの方法
- 肥料の適切な与え方
- 病害虫対策
- 種まきと植え方
- 栽培に必要な資材
- キュウリの成長段階に応じたケア
それぞれ詳しく解説します。
土壌の準備と場所選び

キュウリを育てるには日当たりが良い場所が適しています。
土は水はけが良いのが望ましく、土が固まりやすく水はけが悪い場合はバーミキュライトや軽石を混ぜると良いです。
また、反対に土が砂っぽくて保水性が悪い場合はピートモスやコンポストを混ぜます。
土は植え付けの2週間前に耕して苦土石灰を撒き、1週間前に肥料を与えましょう。
水やりの方法
キュウリは成長に合わせて水やりの方法を変える必要があります。
種まき後は表面の土が乾燥しないようにこまめに水やりをしてください。
植え付け後は、苗が根付くまで表面の土が乾燥したら、気温が高い日中を避けて水を与えます。
目安は1週間に1、2回で、プランターならば乾燥しやすいので毎日の水やりが望ましいです。
収穫期は多くの水分を必要とするので、多めに水やりをしましょう。
肥料の適切な与え方
キュウリは 生育初期は窒素が多め、中盤以降はリン酸・カリウムを重視します。
ホームセンターやネット通販サイトで売られている「野菜の肥料」、「キュウリ用肥料」などがおすすめです。
定植前の元肥では1㎡あたり150g〜200g与え、定植して3週間ほどしたら追肥し、そこからは10日に1回追肥します。
量は一回で1㎡あたり60g〜70gを目安にしてください。
病害虫対策

キュウリがかかりやすい病気は20種類以上あり、キュウリに付きやすい害虫は6種以上あります。
しかし病害虫問題は、予防や発症後又は害虫の発生後の対応によって対処可能です。
キュウリの代表的な病気、うどんこ病と、代表的な害虫、ウリハムシについて、それぞれの特徴と正しい対処法を確認して美味しいキュウリを収穫しましょう。
うどんこ病
- 葉や茎、つる、つぼみに白い斑点が広がる
- 白い斑点は次第に黒くなり、枯れる
- キュウリの味が落ちる
うどんこ病を防ぐためには土の水はけを良くして根を強くし、株自体を丈夫にすることが重要です。
肥料過多も株を弱くし、病気が発症する原因となります。
株どうしの間隔を空け、摘心等で不要な葉を摘み取り、風通しと日当たりを良くすることで予防可能です。
病気になったら患部を速やかに切り取り、症状が重い場合には市販の薬剤を散布しましょう。
ウリハムシ
- 成虫は7〜9mmの黄褐色の甲虫
- 成虫は葉を食べ、幼虫は根を食べる
- 葉に丸や楕円の穴ができたり、網目状になったりする
ウリハムシを予防するには防虫ネットを全体にかけて害虫の侵入を防ぎます。
市販の植物用害虫スプレーも効果があり、ネギやニンニクなどの強い匂いも嫌うため、近くで栽培するのも良いでしょう。
害虫が付いた場合は手やテープで取り、作物用の殺虫剤や農薬などをまくと再発が防止できます。
ウリハムシ
- 成虫は7〜9mmの黄褐色の甲虫
- 成虫は葉を食べ、幼虫は根を食べる
- 葉に丸や楕円の穴がができたり、網目状になったりする
ウリハムシを予防するには防虫ネットを全体にかけて害虫の侵入を防ぐのがおすすめです。
市販の植物用害虫スプレーを使うなども効果があります。
ウリハムシはネギやニンニクなどの強い匂いを嫌うため、近くで栽培するのも良いでしょう。
もしも害虫が付いてしまったら手やテープで取り、作物用の殺虫剤や農薬などをまくと再発が防止できます。
種まきと植え方
キュウリの種は種まき用のビニールポットに蒔くのが一般的です。
成長後に土やプランターなどに植え替えましょう。
種まきの手順は以下の通りです。
- ポットに種を蒔く
- 芽を間引く
- 定植する
それぞれ詳しく説明します。
① ポットに種を蒔く
まずは種まき用のポットを用意してください。
ホームセンターなどで購入できるビニール製の小さい黒のポットがおすすめです。
ポットに種まき用の土を入れ、軽く押さえて平らにならし、土の中央に直径3cm、深さ1cm程の穴をあけて1つの穴に種を3粒、それぞれを離して蒔きます。
種を蒔いたら5mmほど土を被せ、表面をならして軽く水を与えてください。
土の温度が25度ほどに保たれることが望ましいので、室内で育てるのもよいでしょう。
② 芽を間引く
キュウリは4日ほどで発芽します。
芽が出たら、子葉が開いたら元気な2本を残すよう間引き、葉が3枚になるタイミングに、1本になるように間引きます。
この頃は土の温度が20度になるのが望ましいため、室内で温度が高くなりすぎない場所に置きましょう。
ポットどうしが近く、葉が触れ合うほどでは風通しが悪く病気の原因になるため、葉が触れ合わない程度にポットを離して管理しましょう。
③ 定植する
定植前に土に肥料を混ぜて水をやり、定植に適した土を作ります。
定植日はよく晴れた日中を選びましょう。
当日に植え穴を少し浅めに掘って、その脇に50cm間隔で支柱を立ててネットを張ります。
苗と、植え穴に水をしっかりあげたら、苗の根を傷つけないよう気をつけて苗を植え穴に入れ、浅く土を被せます。
つるが伸びてきたらネットに誘引してください。
栽培に必要な資材
キュウリの栽培に最低限必要となる資材は以下の通りです。
- キュウリの種
- 水
- 種まき用のビニールポット
- 種まき用の土
- 発芽促進用の肥料
- 培養土または畑の土
- 苦土石灰
- 定植用の肥料
- キュウリの苗を支える支柱やネット
- 苗を支柱に誘引する紐
必要に応じてスコップや剪定バサミ等もあると便利です。
キュウリの成長段階に応じたケア
キュウリは成長段階に応じて以下のようにこまめなケアが必要です。
ケアを怠ると成長しにくくなったり、収穫量が落ちたりするので注意しましょう。
キュウリの成長段階に応じたケアは以下の通りです。
- 発芽期:温度管理
- 苗期:間引く
- 定植期:誘引する
- 成長期:摘心する
- 収穫期:摘果する
発芽期:温度管理

キュウリの種は土の温度が25度〜30度でなければ発芽しません。
暖かな室内や温室などで育成し、発芽を促します。
保温マットやパネルヒーターを使うのもおすすめですが、高温になりすぎないよう気をつけてください。
4〜5日経っても発芽しない場合は土の温度を測って置き場所などを見直し、暖かな場所に移動しましょう。
苗期:間引く
丈夫な苗を残すために、同じポットから発芽した苗は間引いて最終的に1本にします。
子葉の最初の2枚の葉が出る頃に2本まで減らし、本葉の3枚目の葉が出る頃に1本まで減らしてください。
間引きをしないと密集状態になり、全体に日が当たらない、風通しが悪くなるなどで苗が弱くなります。
間引いた苗は他のポットに移植したり、調理して味わうのも良いです。
定植期:誘引する

茎は支柱に紐で結びつけ、ツルは支柱やネットに巻き付けます。
キュウリのツルは1日に6cmほど伸びるため、伸びるために誘引するなど、こまめな管理が必要です。
ポイントは上向きに伸びるように誘引することです。
ツルを巻きつけたり、軽く結びつけたのちに手を離したときに先端が上を向くよう調整してください。
成長期:摘心する
キュウリの葉が密集し、風通しが悪くなるのを防ぐために成長期には摘心が必要です。
病害虫を防ぎ、収穫量を増やすために適切な摘心をしましょう。
キュウリの脇芽が出てくるところを節といい、摘心では茎を傷つけないように、その脇芽から先を取り除いてください。
まずはキュウリの地面から30cmほどの部分までにある脇芽や雌花を取り除きます。
地面から30〜60cmの節は葉を2枚ほど残すように摘心し、高くなりすぎないように目の高さより高い節は摘み取りましょう。
古くなって色に変わった葉も摘み取ることで病害虫の予防に繋がります。
収穫期:摘果する

実がなったら最初の2、3本を株を疲れさせないために小さめのうちに収穫しましょう。
摘果することで長い間収穫できるようになり、収穫量アップが見込めます。
曲がっているなど、形に歪みのあるキュウリも早期に収穫することで株の負担軽減が可能です。
実が18〜20cmになったらすぐに収穫することも意識してください。
大きくなりすぎるまで収穫しないとその分株に負担がかかり、全体の収穫量に影響します。
キュウリの栽培条件
キュウリには適した栽培の条件が4つあります。
- 置き場所と日当たり
- 温度と湿度の管理
- 用土の選び方
- 風通しと支柱設置
それぞれ詳しく解説します。
置き場所と日当たり
キュウリは日当たりが良い場所を好みます。
プランターで育てる場合は、朝日が当たり、強い西日が避けられる南向きのベランダなども適しています。
温度と湿度の管理
キュウリの栽培に適した温度は昼間約25度、夜間約13度です。
温度が低い場合は防寒の覆いをし、高い場合は断熱の覆いをするなどの管理をしましょう。
キュウリの栽培に適した湿度は約70%のため、60%を下回る場合は散水して湿度をあげましょう。
用土の選び方
種まきの際は種まき用の土が適しています。
定植の際には地植えの場合は土に苦土石灰や肥料を混ぜて用意しますが、プランターで栽培する場合は野菜用の土を選びましょう。
風通しと支柱設置

キュウリは風通しが悪いと病気にかかりやすく、害虫も付きやすくなります。
栽培する場所は風通しの良い場所を選びましょう。
葉や茎、ツルが密集してきたら余分なものを剪定することも大切です。
支柱は定植後に設置が必要で、2本の支柱を上部でクロスさせて固定し、それぞれの支柱の下部30cmは土に差し込み安定させます。
これをいくつか並べて、クロス部分に支柱を横に渡して固定します。
ここにネットをピンと張ってしっかりしたキュウリの支えとしましょう。
キュウリの開花および収穫時期
キュウリの開花から収穫までの流れを確認します。
- キュウリの開花時期
- 収穫に最適な時期の見極め方
- 収穫時期による味の違い
それぞれ詳しく解説します。
キュウリの開花時期

キュウリの花は葉やツルが大きく成長する頃から咲き始めます。
種まきの時期にもよりますが、4月に種を蒔いた場合は5月中頃に開花します。
収穫に最適な時期の見極め方

収穫に最適とされるのは、開花後10日ほど経った時期です。
実の色が薄い黄緑色から濃い緑色になったら収穫します。
収穫が遅れると株が疲れて実ができにくくなるので注意が必要です。
収穫時期による味の違い
キュウリは春に種を蒔く秋夏キュウリ(7〜11月)と、夏に種を蒔く冬春キュウリ(12〜6月)があります。
それぞれのキュウリの味の違いを以下にまとめました。
| 特徴 | 冬春キュウリ | 夏秋キュウリ |
|---|---|---|
| 歯切れ | ◯ | ◎ |
| 青臭さ | ◎ | ◯ |
| さわやかさ | ◯ | ◎ |
| みずみずしさ | ◎ | ◎ |
キュウリは成長段階によっても味が変化します。
成熟する前に収穫した、少し小ぶりのキュウリは緑色が薄めで、皮が薄くえぐみが少なくピクルスなどに適しています。
育ち過ぎて大きくなってしまったキュウリは味が薄まり皮が硬いため、煮物や漬物にされます。
収穫の時間によっても味が異なり、朝収穫されたものが最もみずみずしく、えぐみが少ないです。
さまざまなタイミングでキュウリを収穫し、好みを見つけるのも楽しいでしょう。
キュウリの実がならない原因は?
キュウリの実がならない原因は、次の5つが考えられます。
- 肥料の与えすぎ
- 日当たりが不足している
- 着果不振
- 栄養不足
- 温度や湿度が不適切
それぞれ詳しく解説します。
肥料の与えすぎ
キュウリに肥料を与えすぎると葉やツルが大きく成長する一方で花がつかなくなったり、水分が不足しがちになって実の品質が低下したりします。
肥料は多すぎず少なすぎず、適正量を与えましょう。
日当たりが不足している
日当たりが不足すると根が弱り、生育不良を起こして実がなりにくくなります。
プランター栽培の場合は1日4時間は日が当たるように場所を調整しましょう。
着果不振
キュウリが病気になって実がならない場合もあります。
特に、かかりやすいウドンコ病は株全体を弱らせるので、葉に白い斑点ができたら直ぐにその葉を取り除きましょう。
栄養不足
キュウリは栄養不足になると、葉の色が褪せてツルが伸びにくくなり、花や実がなりにくくなります。
実がなっても収穫量が落ちたり、曲がってしまうので気をつけましょう。
温度や湿度が不適切
キュウリは温度や湿度が高すぎても低すぎても枯れてしまいます。
枯れないまでも萎れる、病気になる、害虫がつく、成長が止まる、実の色が変わる、収穫量が減るなどの問題が起こるため、適切な温度と湿度になるように心がけましょう。
キュウリの増やし方
キュウリの増やし方にはいくつかの方法があります。
それぞれ詳しく解説します。
摘心と摘果の方法

先端の芽を摘むことを摘心、最初の実を摘むことを摘果と言い、これによって収穫量が増やせます。
摘心は支柱やネットを越える芽を摘んで、上に伸びていかないように調整しながら行いましょう。
摘果は最初の実の3本を15cm程度の若いうちに取ります。
挿し木によるキュウリの増やし方
脇芽を摘む際にいくつかのポイントに注意すると挿し木としてキュウリの苗を増やすために使えます。
挿し木をするためにはまず脇芽を鋭利なハサミやナイフで斜めに切り、直ぐに水に挿します。
遮光性のある、栄養ドリンクの空き瓶などを使用すると良いでしょう。
活力剤を使用しながら室内で育成し、根が出たらビニールポットなどで土に根づかせ、新しい芽が出てきたタイミングで定植します。
水耕栽培による増やし方

キュウリを水耕栽培をするためには専用のプランターをホームセンターなどで購入するかペットボトルやバケツの用意が必要です。
挿し木をするのと同様に、切り口を斜めに剪定した脇芽を水に挿し、活力剤を加えて根が出たら茎の回りをスポンジ等で固定して育てていきます。
上手に育てるためには、水質の悪化を防ぎつつ、根が密集しないように広めのプランターやペットボトルなどの容器を選ぶことが重要です。
植え替えの適期と手順
キュウリの植え替えは適切な時期を逃さないよう、次の手順に沿ってポイントを押さえながら進めましょう。
- 植え替えの適期は苗に本葉が3〜4枚生えたころ
- 苗と植え替え先の準備をする
- 植え付ける
植え替えの適期は苗に本葉が3〜4枚生えたころ

植え替えは通常、暖かな春の時期の4月〜5月に行うことが多いです。
最低気温が10度を超えていないとキュウリは苗が萎れるなどの低温障害を引き起こします。
本葉が3〜4枚になっても気温が10度を下回る、霜が降りるという場合は植え替え後に株に覆いをするなどして防寒、防風対策が必要です。
植え替えが6月を過ぎると地域や品種によっては暑さに負けてしまうので気をつけましょう。
苗と植え替え先の準備をする
ず、植え替え先の土壌やプランターを準備し、事前に肥料を混ぜておきます。
プランターを使用する場合は、深さ30cm以上のものを選び、高さ2mほどの支柱を立ててネットを張ってください。
また、キュウリは乾燥に弱いため、植え替えの直前に苗と植え替え先の土に十分な水を与えることが重要です。
植え付ける
苗同士が密集すると病気になりやすく、害虫も付きやすいため、40cmほど間隔を空けて植え付けます。
この際、苗の根を傷つけないよう注意しながら、浅めに土を被せてください。
キュウリは湿度が高いと病害虫が発生しやすいため、根が地表に少し見える程度に浅く植えるのが理想です。
浅く植えることで根が土に早く馴染み、丈夫に育つ効果もあります。
植え替えが終わったら、水を軽く与えて根付きやすくしましょう。
鉢替えのやり方
キュウリは鉢替えにあまり強くないため、ポイントを押さえて丁寧に行いましょう。
鉢替えの手順は以下の通りです。
- 株に水を含ませる
- 根鉢を崩さなないようにして移動する
- 水をやる
株に水を含ませる
植え替え先の鉢やプランターと土が用意できたら株の準備をします。
まずは株の元気があるかを確かめてください。
植え替え前に病害虫の影響を受けていたり、温度や湿度、日差しの影響で株が萎れかかっている場合は鉢替えは難しくなります。
キュウリは乾燥に弱いため、植え替え前に株の根へ十分に水を与えておくことが大切です。
株に水を含ませることで根鉢を崩さずに植え替えることも楽になります。
根鉢を崩さなないようにして移動する
根を傷つけないように、根が密集している根鉢は丁寧に扱いましょう。
鉢から株を取り出すときは横倒しにして鉢の側面を叩くと綺麗に取り出せます。
株と株の間が20cm前後になるよう調整したら株が動かないよう土を周りに詰めて軽く土の表面をならしてください。
軽く土の表面をならすことで株が定着しやすくなり、株の向きも整います。
水をやる
最後に水を与えて根の定着を促します。
植え替え後は根付くまでは多くの水を必要としませんが、土の表面が乾いた場合は軽く水やりが必要です。
また、必要に応じて支柱を立て直し、ネットを張り直してツルを巻き直しましょう。
鉢替え後は株が弱りやすいため、室内で温度や湿度を管理したり、日陰に置いて強い日差しを避けるなど、細やかな世話が必要です。