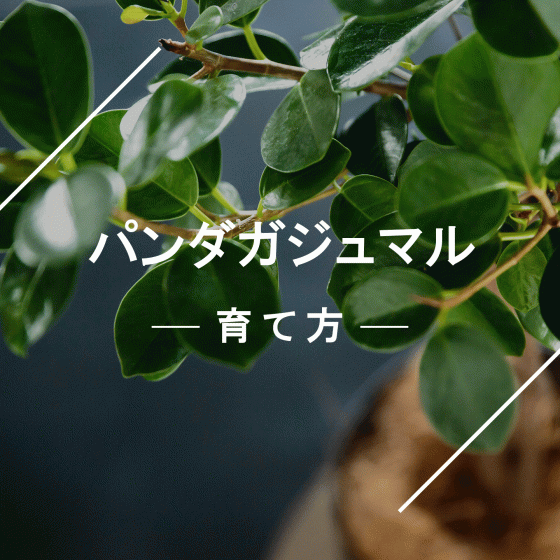ゴーヤーの育て方
公開日 2025年03月17日
更新日 2025年04月22日
育てやすさ
育て方の難易度は普通レベルです。
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。
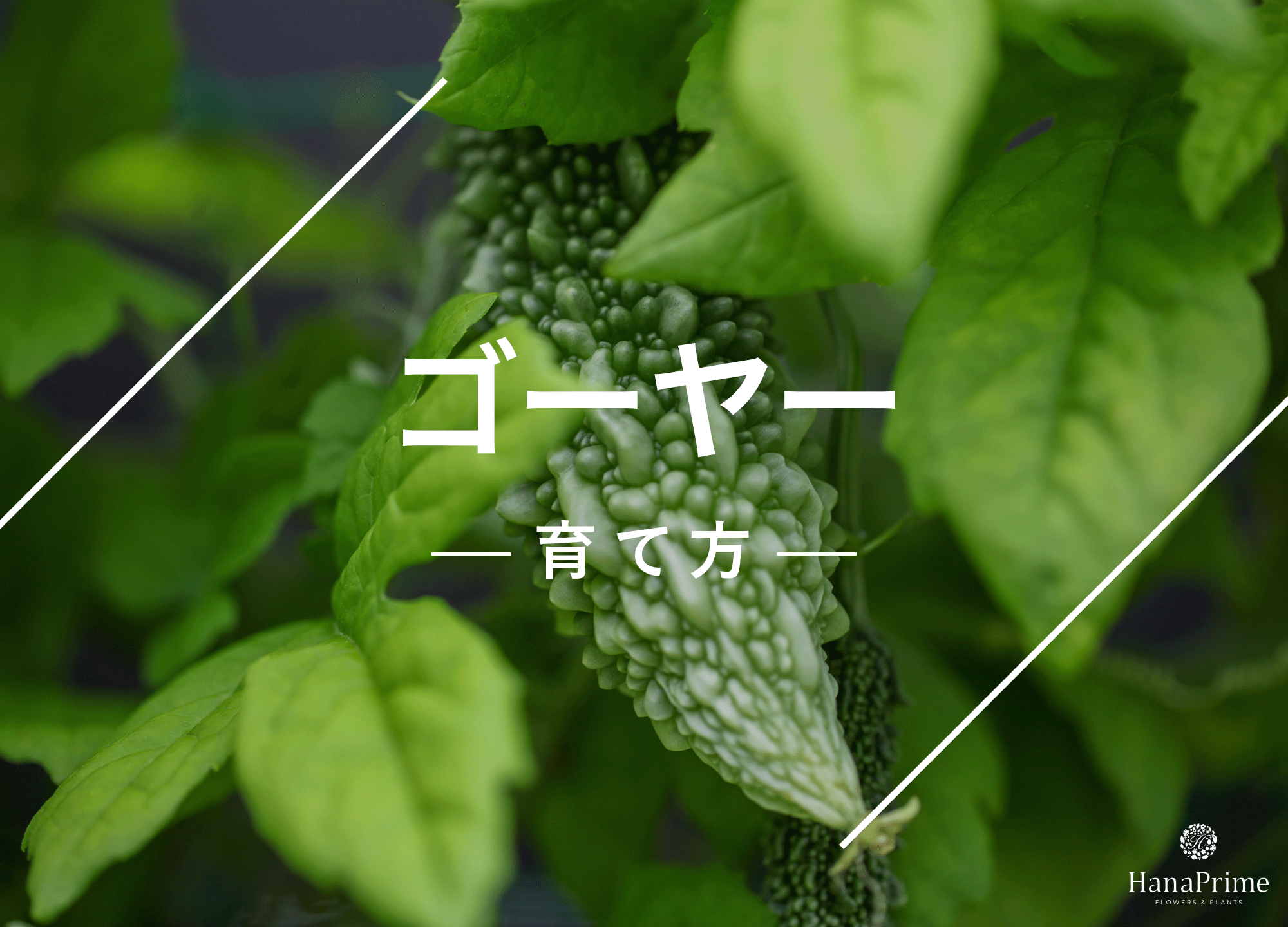
ゴーヤーの基本情報
| 植物名 | ゴーヤー |
| 学名 | Momordica charantia |
| 和名 | ツルレイシ(蔓茘枝) |
| 英名 | Bitter melon、Bitter gourd |
| 別名 | ニガウリ |
| 原産地 | 熱帯アジア、インド |
| 科名 | ウリ科 |
| 属名 | ツルレイシ属 |
| 開花時期 | 6月~8月 |
ゴーヤーは、ウリ科のつる性植物で、主に緑色の果実を野菜として利用します。
健康食として人気があり、夏の代表的な野菜のひとつでイボに覆われた果実の外観が特徴的です。
ゴーヤーの開花時期は6月~8月で、花は朝に開き、午後にはしぼむことが多く、気温が20~30℃の時期に開花が活発になります。
適切な環境で育てると、夏の間たくさんの花が咲き、多くの実を収穫できるでしょう。
月別栽培カレンダー
種まき
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
植え付け・植え替え
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
肥料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
開花
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
種類と品種

ゴーヤーにはさまざまな品種があり、大きく分けて長型、中型、短型、白色種などに分類されます。
| 品種 | 大きさ(㎝) | 甘味 | 味の濃さ | フルーティ | 酸味 | さっぱり感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さつま大長れいし | 40以上 | △ | ◯ | △ | 弱い | 高い |
| あばしゴーヤー | 15~20 | × | ◎ | × | 強い | 普通 |
| 白ゴーヤ(しろにがくん) | 20~25 | ◎ | ◯ | ◎ | なし | 高い |
| えらぶ | 20~30 | ◯ | ◎ | ◯ | 弱い | 普通 |
| 球形ゴーヤ | 10~15 | ◯ | ◯ | ◎ | 普通 | 高い |
さつま大長れいしは、長型ゴーヤーで、苦みが少なく、あばしゴーヤーは、表面のイボが大きく、一般的な品種より苦みが強め。
白ゴーヤは、苦みが少なく、えらぶは、中型で育てやすく適度な苦みを持ちます。
球形ゴーヤは、肉厚で食感が良く、苦みは控えめで食べやすいでしょう。
栄養成分と健康効果
| 栄養成分 | 健康効果 |
| ビタミンC | 免疫力を高める |
| カリウム | 余分な塩分を排出し、高血圧予防に役立つ |
| 食物繊維 | 便秘解消に役立つ |
| モモルデシン | 食欲を増進し、血糖値を下げる効果あり |
| チャランチン | 血糖値を下げる作用 |
| 葉酸 | 貧血予防や妊娠中の栄養補給に役立つ |
| 鉄分 | 貧血予防に効果的 |
| マグネシウム | ストレス軽減や血圧の安定に効果あり |
| β-カロテン | 皮膚や粘膜の健康を保ち、視力維持にも効果あり |
ゴーヤーは、ビタミンCとモモルデシンなどを含み、疲労回復や夏バテ防止に役立つ野菜です。
栄養価が高く、美肌効果やアンチエイジングに役立つため、美容意識が高い人にもおすすめ。
健康に必要な栄養素を多く含むゴーヤは、日々の食生活に取り入れたい野菜のひとつです。
旬の時期と味の違い
最も美味しい旬は、露地栽培のゴーヤーが豊富に出回る7~8月で、苦みが強く濃厚な味です。
春と秋は、苦みが控えめで食べやすいため、ゴーヤーが苦手な方や食べなれていない初心者におすすめ。
冬は、温暖な地域でのハウス栽培が中心で、流通量が少なく、食べる機会が少ないですが、苦みも少なくやわらかいのが特徴です。
ゴーヤーの苦みの強さは季節によって変わるので、好みに合わせて旬を楽しんでみてはいかがでしょうか。
ゴーヤーの歴史と主な生産地
ゴーヤーは、15世紀頃にアジアから中国へ渡り、16世紀末ごろ中国から琉球王国へ渡ってきました。
そして、17世紀ごろに琉球から日本に伝わったと言われており、1900年代に全国的にもゴーヤーが食されるようになります。
現在の主な生産地は中国・インド・熱帯アジア、日本では沖縄・群馬・九州地方などです。
地域ごとや栽培方法ごとに特徴のある品種が多く、それぞれの産地で独自に進められています。
ゴーヤーの育て方
ゴーヤーを上手に美味しく育てるためには、適切な管理が重要です。
- 土壌の準備と場所選び
- 水やりの方法
- 肥料の適切な与え方
- 病害虫対策
- 種まきと植え方
- 栽培に必要な資材
- ゴーヤーの成長段階に応じたケア
上記のポイントに分けて、解説します。
土壌の準備と場所選び

ゴーヤー栽培には、適切な場所選びと土壌作りが欠かせません。
以下にポイントをまとめました。
- 日当たりが良く、通しが良い場所
- ネットや支柱を立てられる環境
- 水はけが良く、肥沃な土壌が理想的
- pH 6.0~6.5(やや弱酸性~中性)が適切
- 植え付けの2週間前に、堆肥や苦土石灰を混ぜる
ゴーヤーは、1日6時間以上の直射日光が当たる場所で、風通しの良い場所が最適ですが、強風には弱いため注意が必要です。
市販の野菜用培養土でも大丈夫ですが、自作する場合は、pH 6.0~6.5(やや弱酸性~中性)が適しています。
植え付けの 2週間前に、堆肥や苦土石灰を混ぜて土壌を整え、1週間ほど寝かせてから植え付けましょう。
水やりの方法
ゴーヤーは乾燥に強い一方で過湿に弱いため、適切な水やりが非常に大切です。
- 発芽するまでと根付くまでは用土の表面が乾いたら水やりが必要
- 果実がなり始めたら早朝と夕方前の1日2回水やりをする
- 朝の水やりをしっかり行う
- 葉や茎ではなく根元にしっかり水をかける
ゴーヤーは水を好みますが、過湿になりすぎると根腐れの原因になるため、土の表面が乾いているのを確認してから、水を与えましょう。
高温期の水やりは、根や葉などを傷めるので、涼しい時間帯に水やりをするのがポイントです。
夜間の水やりは、低温で苗の生育に悪影響を及ぼす可能性があるため、なるべく避けましょう。
肥料の適切な与え方
ゴーヤーを大きく立派に育てるためには、肥料を適切に与えることが重要です。
成長が早いため、植え付け前にしっかりと肥料を与えましょう。
ゴーヤーは栄養を多く必要とするため、生育期には定期的な追肥が大切です。
1回目の追肥は、植え付けから2〜3週間後に行い、2回目以降の追肥になると実がつき始めたら1〜2週間に1回のペースで肥料を与えます。
また、収穫が始まったら2週間に1回を目安に肥料を追加し、実のつきがよくなるようにしてください。
肥料をあげすぎると根が傷むことがあるため、適量を守ることが大切です。
病害虫対策
ゴーヤーは、苦味成分が含まれているため、比較的害虫が発生しにくい野菜ですが、完全に無害が付かないわけではありません。
ゴーヤーに発生しやすい代表的な害虫を以下にまとめました。
アブラムシ
- 新芽や葉の裏に群がって汁を吸う
- ウイルス病を媒介することがある
アブラムシ対策は、発見したらすぐに駆除しましょう。
水で洗い流したり、粘着テープで取ったりすることで駆除することができます。
木酢液や牛乳スプレーを散布して、窒息させるのもひとつです。
ウリハムシ
- オレンジ色や黒色の小さな甲虫
- 葉に穴を開ける(レース状に食べる)
- 幼虫は根を食害し、成長を阻害する
成虫を見つけたら手で捕まえて駆除します。
ただ、ウリハムシの成虫はとても素早く動くため、注意しましょう。
寒冷紗や防虫ネットで物理的に防いだり、黄色い粘着トラップで誘引・捕獲したりするのも有効です。
ハダニ
- 乾燥した環境で発生しやすい
- 葉の裏に付着し、吸汁して白い斑点ができる
- 大量発生するとクモの巣のような糸を張る
ハダニは水に弱いため、葉の裏に水をかけて洗い流すことが大切です。
定期的な葉水が有効で、湿度を上げるのもひとつ。
生物農薬として市販されている天敵のチリカブリダニを活用するのも有効でしょう。
ネコブセンチュウ
- 根に寄生し、根こぶを作る
- 水や養分の吸収を阻害し、成長が悪くなる
同じウリ科を続けて育てないことで、連作を避けることが重要です。
センチュウを抑制する効果があるマリーゴールドを植えて、土壌改善するのも良いでしょう。
太陽熱消毒や市販の消毒液などを使用し、土壌消毒を行うのも大切です。
種まきと植え方
ゴーヤーは育てやすい野菜ですが、発芽しにくい性質があるため、種まきと植え方の工夫が大切です。
ゴーヤーは、以下の手順で種まきと植え付けを行いましょう。
- 発芽率を上げるコツを実施
- 土壌を準備し、種をまき管理
- 発芽後の管理の実施
- 苗の植え付け
それぞれ順番に解説します。
発芽率を上げるコツを実施
ゴーヤーの種は、発芽率を上げるためのコツがあるため、実施しましよう。
ゴーヤーの種は硬いので、ヤスリや爪切りで硬い部分を削ると吸水しやすくなります。
1日のうち8〜12時間ほど水に浸けると、発芽しやすくなり、ぬるま湯を使うとさらに効果的です。
発芽させてから植えるとより良いので、湿らせたキッチンペーパーに包んで、暖かい場所で2〜3日置くと良いでしょう。
土壌を準備し、種をまき管理

ゴーヤーは水はけがよく、栄養豊富な土を好むため、元肥を混ぜて栄養の良い土を作りましょう。
直播きする場合は、1カ所に2~3粒ずつまき、深すぎると発芽しにくいので深さ1〜2cmに浅く植えます。
ポットで育苗する場合は、9cmポットに培養土を入れ、1ポットにつき1~2粒の種を撒いて下さい。
発芽するまでは、土が乾かないように毎日水を与え、気温が低い場合はビニールや不織布で覆い、防寒・保温をします。
発芽後の管理の実施

発芽直後は根が浅いため、土の表面が乾かないように適度に水を与えます。
ただし、過湿にすると根腐れを起こしやすいため注意が必要です。
最低でも1日5~6時間の日光が必要であるため、日当たりの良い場所で育てなければいけません。
ゴーヤーの幼苗は、風で倒れやすいので、風が強い日は防風ネットを活用しましょう。
苗の植え付け

ゴーヤーの苗を枯らさずに植え付ける方法は、丈夫な根と本葉が立派に育っている時です。
苗の植え付けに適しているタイミングとして、霜や低温に弱いため、寒さがなくなってから植えて下さい。
苗は、茎が太く葉の色が濃いものが良く、ひょろひょろと伸びすぎたものは避けます。
植え付けと同時にネットや支柱を設置すると、より元気に苗が育つでしょう。
栽培に必要な資材
ゴーヤーの栽培に必要な資材は、以下の通りです。
- 土
- 石灰
- 堆肥
- 化成肥料、有機肥料
- ゴーヤーの種、苗
- ポット、プランター
- 支柱
- 支柱クリップ・ひも
- ネット
- ビニール
- 防虫ネット
- 農薬
ゴーヤーは、つる性の植物なため支柱設置がとても重要で、180~200cmの大きい物を準備します。
種か苗から育てるのか、地植えかプランター栽培かによって、必要な資材は変わってくるため、臨機応変に対応しましょう。
ゴーヤーの成長段階に応じたケア
ゴーヤーの成長段階に応じたケアは、美味しく立派な果実を育てるのに欠かせません。
苗を購入して栽培する場合、成長段階に応じたケアは以下の通りです。
- 初期成長期:適切な温度と湿度の管理
- 成長期:葉や茎の成長を促すポイント
- 開花期:受粉をしっかりさせる
- 果実形成期:果実を大きくするコツ
- 収穫期:果実を傷つけないためには
① 初期成長期:適切な温度と湿度の管理
ゴーヤーは、温暖な気候を好むため、気温は15℃以上が望ましく、理想的な昼間の気温は25~30℃、夜間は15℃以上を維持しましょう。
寒さに弱いので、霜や寒風から守るために、寒い時期はビニールや不織布で覆うなどして温度管理を行います。
ゴーヤーは、湿度が高すぎても乾燥しすぎても良くなく、湿度は50~70%に保つことが大切です。
過湿し過ぎてしまうと、根腐れの原因になるため、注意しましょう。
② 成長期:葉や茎の成長を促すポイント

ゴーヤーはつる性植物なので、成長が進むとつるが伸びます。
支柱やネットを設置して、つるが絡みやすいように誘引することが重要です。
成長初期の段階では、窒素を含む肥料を与えると、葉や茎の成長を促進します。
化成肥料(窒素・リン酸・カリウムがバランス良く含まれたもの)を2週間に1回施肥しましょう。
肥料の与えすぎには注意し、特に窒素過多だと茎や葉ばかりが成長し、花や実がつきにくくなるため、バランスよく施肥を行います。
③ 開花期:受粉をしっかりさせる

ゴーヤーは雄花と雌花が別々に咲き、両方の花が受粉しないと実がつきません。
受粉を助けるために、人工受粉が効果的で、雄花の花粉を雌花の柱頭に付けることで、着果率が高まります。
自然の受粉者を呼び込むため、周囲に花を植えることも良い方法です。
また、害虫の被害を防ぐためには、防虫ネットを使うことも検討してみて下さい。
④果実形成期:果実を大きくするコツ

果実が大きくなる時期には、十分な水分が必要で、水やりはこまめに行い、土が乾燥しないように保つことが大切です。
果実がつき始めたら、リン酸やカリウムを多く含む肥料を与えて、成長を助けるために2週間ごとに追肥を続けます。
液体肥料を使用すると、根から早く吸収され、効果的です。
害虫が果実にダメージを与えないように、防虫ネットや無農薬の防虫液を使用します。
➄収穫期:果実を傷つけないためには

ゴーヤーは長さ20~25cm、表面のイボがしっかりしている状態が収穫に適しています。
熟しすぎると苦味が強くなるので、少し早めの収穫が理想的です。
こまめに収穫することで次の実がつきやすくなります。
収穫時は、果実を傷つけないように、ハサミや剪定ばさみで収穫するのがおすすめです。
手で引っ張るとつるを傷つける恐れがあるため、注意しましょう。
ゴーヤーの栽培条件
ゴーヤーを栽培するためには、条件があります。
- 置き場所と日当たり
- 温度と湿度の管理
- 用土の選び方
- 風通しと支柱設置
それぞれ順番に解説します。
置き場所と日当たり
ゴーヤーは、日当たりを好む植物のため、直射日光を6時間以上浴びる場所が理想です。
直射日光がよく当たる場所に置くと、葉が元気に育ち、花や実もつきやすくなります。
しかし、直射日光が強すぎると、葉が焼けてしまうこともあるので、午前中の早い時間帯に日光を浴びる場所が最適。
ゴーヤーは、つるを伸ばすので、支柱やネットを設置できる広め場所を選ぶことが大事です。
また、水性の良い土壌で育てることが重要で、プランターで育てる場合、底に排水穴がしっかりと開いているものを選びましょう。
温度と湿度の管理
ゴーヤーは温暖な気候を好み、理想的な温度は昼間25~30℃、夜間15~20℃です。
ゴーヤーは寒さに非常に弱いので、最低気温が10℃以下になると生育が停滞するため春~初夏に植え付けるのが良いでしょう。
日中は直射日光で温度が上がる場合、風通しを良くすることで温度がこもり過ぎないようにします。
ゴーヤーは湿度が50~70%程度の環境を好み、過湿になりすぎると根腐れの原因になるため、気をつけましょう。
湿度が低い場所で栽培する場合は、週に1~2回、葉に霧吹きで水をかけると湿度を保つことができます。
温度と湿度をしっかり管理することで、ゴーヤーが元気に育ち、実もたくさん収穫できるはずです。
用土の選び方
ゴーヤーに適した土壌は、排水性、通気性が良く、栄養分が適度に含まれていることが理想です。
市販の野菜用培養土でも十分ですが、自作する時は赤玉土、腐葉土、バーミキュライトなどを組み合わせ、土が酸性に傾きすぎている場合は石灰で調整しましょう。
また、ゴーヤーはウリ科のため、連作障害が生じることがあります。
プランターで育てる場合は、必ず苗植え前に土を変え、地植えの場合は、同じ場所で育てるのをやめるのが吉です。
風通しと支柱設置

ゴーヤーは風通しが良い場所を好み、通気性の良い環境で育てることで、病気やカビの発生を防ぎ、健康的に成長します。
ゴーヤーはつる性の植物なので、支柱やネットを設置して、つるが伸びるスペースを確保しましょう。
以下に、支柱の設置方法や特徴をまとめました。
| 支柱の種類 | 特徴 |
| 単支柱 | 設置がシンプルで、ゴーヤーのつるが集中的に成長しやすい |
| 複数支柱 | ゴーヤーのつるが広がりやすく、空間を効率的に活用でき、収穫しやすい |
| 金属製支柱 | 頑丈で長期間使用可能であり、強風や重い実にも耐えられる |
| 竹支柱 | 軽量で扱いやすい |
| プラスチック製支柱 | 耐久性は比較的低いが、コストが安い |
| ネット支柱 | 網目に沿ってつるが絡みやすく、空間の利用効率が良い |
ゴーヤーの開花および収穫時期
ゴーヤーの開花および収穫時期について、解説します。
- ゴーヤーの開花時期
- 収穫に最適な時期の見極め方
- 収穫時期による味の違い
ひとつずつ説明します。
ゴーヤーの開花時期

ゴーヤーは通常、植え付けから約2ヶ月後に開花が始まり、春に植え付けを行った場合、6月~7月頃に最初の花が咲き始めます。
温暖な気候で育てると、開花が早く、寒冷地ではやや遅れることも。
雌花と雄花が混在して咲き、自家受粉ではなく、風や昆虫によって受粉が行われます。
もし、受粉がうまくいかない場合、手で花粉を雌花に移す方法もひとつです。
開花後10日~2週間で受粉がうまくいくと、雌花の根元が膨らみ、ゴーヤーの実が成長します。
収穫に最適な時期の見極め方

ゴーヤーの収穫時期は、品種にもよりますが実が約15~20cmの大きさに達し、色が濃い緑に変わったタイミング。
皮が滑らかでツヤがあり、しっかりとした色合いの実が食べ頃です。
実が成長しすぎると、硬くなり、苦味も増すので、若い実を早めに収穫することをおすすめします。
ゴーヤーは1株から複数回収穫できるので、早めに収穫して、次の実を育てるスペースを作ることが重要です。
収穫時期による味の違い
ゴーヤーは、夏が旬の野菜ですが、栽培方法の違いによって、収穫量の違いがあっても通年収穫されています。
以下に、収穫時期による味の違いを表でまとめました。
| 特徴 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|
| 甘味 | × | △ | ◯ | ◎ |
| 味の濃さ | △ | ◯ | ◎ | ◯ |
| フルーティ | × | △ | ◯ | ◎ |
| 酸味 | △ | △ | ◯ | × |
| さっぱり感 | ◯ | △ | ◯ | △ |
春に収穫されたゴーヤーは、皮がやや薄く、甘味が少ないため、フルーティさも感じにくいです。
夏のゴーヤーは、甘味はまだ控えめで、適度な苦味と爽やかな風味があるので、サラダやジュースにもおすすめ。
秋のゴーヤーは、夏に比べるとやや苦味が抑えられ、甘味が増し、苦味が少ないとされています。
収穫量が少ない冬のゴーヤーは、甘味が最も強く、苦味がほとんど感じられません。
ゴーヤーの実がならない原因は?
ゴーヤーの実がならない原因を以下に分けて、解説します。
- 肥料の与えすぎ
- 日当たりが不足している
- 着果不振
- 栄養不足
- 温度や湿度が不適切
ひとつずつ説明します。
肥料の与えすぎ
過剰な窒素肥料は、葉や茎の成長を促進しますが、過剰に与えると、葉や茎が大きく育ちすぎる一方で、花や実の成長が妨げられます。
これにより、ゴーヤーの実がならず、葉や茎の成長ばかりが目立つという状態に陥る可能性も。
また、肥料が多すぎると、土壌が肥沃すぎて根がダメージを受けることがあるでしょう。
過剰な肥料は、根に負担をかけ、健康的に根を育てることができなくなるため、結果的に実をつける力が弱まります。
適切な肥料の使用量を守り、肥料管理を行うことで、実つきが良くなり、大きく育つゴーヤーを育てることができるはずです。
日当たりが不足している
ゴーヤーは熱帯植物であり、強い日光を必要で、十分な日光を浴びることで、健全に成長し、実がしっかりとつくようになります。
日当たりが不十分だと、光合成がうまく行われず、エネルギー供給が不足することも。
その結果、花が咲きにくくなり、実がつきにくくなってしまいます。
屋外の南向きの場所や、日陰になることが少ない場所が適しており、周囲に他の植物が密集しないように注意が必要です。
屋内栽培や日光が不足しがちな場所では、人工照明を使用して、必要な光を補いましょう。
着果不振
着果不振とは、花は咲くが実がつかない状態のことを指し、ゴーヤーを栽培する際に悩まされることがあります。
原因は、以下の通りです。
- 風や虫による受粉がうまく行われない
- 昆虫の活動が少ない
- 過密な栽培
- 温度や湿度の不適合
- 栄養のアンバランス
以上の問題を解決するのは、適切な受粉、温度管理、肥料のバランス、適切な水やりと間隔を空けた栽培が必要です。
環境を整えて、ゴーヤーが健康的に成長できるように工夫することが、実をしっかりつけるために欠かせません。
栄養不足
栄養不足だと、全体に栄養が行き渡らず結果的に実がならない原因になります。
栄養不足の原因は、以下の通りです。
- 追肥不足
- 有機物や栄養素が不足している
- 適切な水やりが出来ていない
- 病害虫や過湿で根が傷み、栄養吸収能力が低下する
栄養不足は、きちんと管理することで防ぐことができ、対策が必要不可欠です。
適切に追肥を行い、土壌の改良や適切な水分管理をすると、栄養不足になることはありません。
葉の色や成長具合を観察し、異常があれば早めに施肥や剪定を行います。
温度や湿度が不適切
ゴーヤーは、気温が15℃以下になると成長が鈍化し、花が咲きにくくなります。
また、日中の温度が低いと花粉がうまく飛ばず、受粉が不十分になり、実がつきにくくなる原因にも。
温度管理だけでなく、湿度管理も大変重要な要素であるため、風通しを良くしたり、適切な水やりをしたりして管理が必要です。
ゴーヤーの栽培には、温暖で安定した気候が必要で、環境を整えることで健全な成長と実の収穫を促進できます。
ゴーヤーの増やし方
ゴーヤーの増やし方のポイントは、以下の通りです。
ひとつずつ紹介します。
摘心と摘果の方法

摘心は、ゴーヤーの枝先を切り取ることで、主に横方向に枝を広げさせ、株を多枝化し、より多くの花や実をつけやすくする方法です。
タイミングは、苗が20~30cm程度に成長した頃で、摘心後、側枝がしっかりと出てきて、より多くの花や実をつけるようになります。
摘果は、実が多くつきすぎている場合や、成長が不十分な実を取り除き、栄養の供給を集中させ、より品質の良い実を育てる方法です。
ゴーヤーの実が小さくてまだ成長していない段階、または実が多くなりすぎた場合に行います。
摘心と摘果は成長を促進し、収量を増やすために重要で、実施することで健康で収量の多いゴーヤーを育てることが可能です。
挿し木によるゴーヤーの増やし方
挿し木による増やし方は、他の植物に比べると少し難易度が高めですが、正しい方法を知れば成功することもあります。
ゴーヤーの挿し木による増やし方の手順をまとめました。
- 枝を切り取る
- 葉を取り除く
- 挿し木を土に挿す
- 水やりと環境管理
枝を切り取る
新しい茎や枝(成長したての枝)を使うと成功しやすく、健康なゴーヤーの枝を10~15cm程度切り取ります。
切り口は斜めに切ることで、水分の吸収がしやすくなるでしょう。
葉を取り除く
切り取った枝の下部の葉を2~3枚程度残し、その他の葉を取り除きます。
葉が多すぎると水分が蒸発してしまうため、適切な枚数を残すことが大切です。
挿し木の切り口に発根促進剤をつけることで、発根が早く進みます。
挿し木を土に挿す
挿し木用の鉢やトレイに排水性の良い土を入れ、枝を1/3程度土に埋めます。
挿し木を軽く押し込んで、土がしっかりと枝を支えるようにしましょう。
水やりと環境管理
挿し木をした後、土が乾かないように適切に水やりをしますが、水分過多にならないよう注意しましょう。
挿し木をした場所は、湿度の高いところに置きます。
湿度を保つために、ビニール袋や透明なカバーをかけると良いです。
水耕栽培による増やし方
水耕栽培は土を使わず、水と栄養素を使って植物を育てる方法で、ゴーヤーも水耕栽培で育てることができます。
ゴーヤーの成長に合わせて、大きめの容器を選び、大きくなるにつれて根が広がるため、十分なスペースが必要です。
水中の酸素が不足しないように、エアポンプやエアストーンを使って酸素を供給しましょう。
水耕栽培では、水質管理と栄養管理が特に重要で、定期的に水を交換し、古くなった栄養液を取り替えます。
土を使わずに水と栄養液で育てることができ、管理さえしっかりと行えば、効率的にゴーヤーを育てられるはずです。
植え替えの適期と手順
ゴーヤーの苗を購入した場合や、種まきで育てた苗を定植する場合、根が鉢の中で窮屈に感じるようになった時が植え替えの適期です。
植え替えの手順を以下にまとめました。
- 現在の鉢から苗を取り出す
- 根を整える
- 新しい鉢に植え替える
- 支柱を立てる
- 植え替え後の管理徹底
現在の鉢から苗を取り出す

ゴーヤーを優しく鉢から取り出します。
根が鉢の壁に張り付いている場合は、軽く鉢を叩いて土を崩し、根をほぐすことが大切です。
根を傷つけないように注意しましょう。
根を整える
根が密集していたり、曲がっていたりする場合は、優しく根をほぐして広げます。
根が健康であれば、切る必要はありませんが、長く伸びすぎている部分を少し切り取ってください。
傷んだ根や古い根も切り取ることをおすすめします。
新しい鉢に植え替える
新しい鉢に排水性の良い土を1/3程度入れます。
ゴーヤーの苗を中央に置き、根を広げた後、周りを土で埋めましょう。
根がしっかりと土に埋まるようにしますが、根の部分が深くなりすぎないよう注意します。
支柱を立てる

ゴーヤーはつる性植物なので、支柱やネットを使って、成長を支えるために設置するのが大切です。
特に支柱を早めに設置しておくと、つるが絡まる場所が確保され、成長しやすくなります。
植え替え後の管理徹底
植え替え後は、土が乾燥しないように十分な水やりを行います。
ただし、水はけが良すぎると根が水分を吸収できないので注意が必要です。
鉢替えのやり方
ゴーヤーの苗が鉢で育ち根が張りすぎてきた場合や、葉の成長が止まってきたと感じる場合には鉢替えのサインです。
苗の高さが15~20cm以上になり、鉢底から根が出始めたら鉢替えを検討しましょう。
根を傷めないように、そっと取り出し、丁寧に扱うことを心掛けます。
鉢替え直後は、たっぷりと水を与えて根と土をしっかりなじませ、表面が乾いたら水を与えます。
根詰まりを防ぎ、より大きな鉢に移すことで成長がスムーズに進むでしょう。