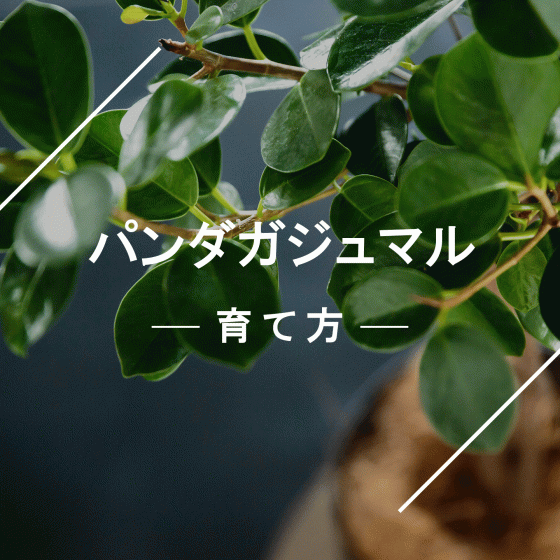アスパラガスの育て方
公開日 2025年04月03日
更新日 2025年06月06日
育てやすさ
育て方の難易度は普通レベルです。
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

アスパラガスの基本情報
| 植物名 | アスパラガス |
| 学名 | Asparagus officinalis L. |
| 和名 | オランダキジカクシ |
| 英名 | Asparagus |
| 別名 | マツバウド、セイヨウウド |
| 原産地 | 南ヨーロッパからウクライナ地方 |
| 科名 | キジカクシ科 |
| 属名 | クサスギカズラ属 |
| 開花時期 | 5~7月 |
| 収穫時期 | 4~5月 |
アスパラガスは、春に旬を迎える瑞々しい野菜です。
若い芽や茎を食べるのが特徴で、シャキッとした歯ごたえと優しい甘みがあります。
炒め物やスープ、パスタなど、さまざまな料理に活用できるだけでなく、ビタミンや葉酸、アミノ酸など栄養も豊富です。
多年草なので一度植えると長く収穫を楽しめるのも嬉しいポイント。
大きめのプランターを用意すれば、ベランダでも栽培が可能です。
月別栽培カレンダー
種まき
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
植え付け(大苗)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
植え替え
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
肥料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
開花
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
収穫
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
種から育てる場合は、収穫は種まきから3年目の春になります。
大苗(根株)から育てると、植え付けをした翌年の春に収穫が可能です。
種類と品種

アスパラガスには、大きく分けて次の3種類があります。
- グリーンアスパラガス(緑)
- ホワイトアスパラガス(白)
- パープルアスパラガス(紫)
グリーンとホワイトは同じ品種ですが、育て方が異なります。
ホワイトアスパラガスは、土を寄せて日光を遮ることで白く成長するのが特徴です。
日本各地で栽培されており、さまざまな品種が開発されてきました。
アスパラガスの代表的な品種は下記の通りです。
| 品種 | 色 | 雄・雌 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ウェルカムAT | 緑 | 全雄 | 太さの揃いが良い |
| ガインリム | 緑(紫が混じる) | 全雄 | 耐倒伏性・耐病性・低温伸長◎ |
| グリーンタワー | 緑 | 雌雄混合 | 茎枯病に強い |
| バイトル | 緑 | 雌雄混合 | 極早生種 |
| ゼンユウガリバー | 緑 | 全雄 | 穂先の締りが良い |
| さぬきのめざめ | 緑 | 雌雄混合 | 長くて柔らか |
| 恋むらさき | 紫 | 全雄 | 他の品種より濃い紫 |
| 満味紫 | 紫 | 雌雄混合 | 遮光でホワイトやピンクになる |
| ガインリム | 白 | 全雄 | 耐倒伏性・耐病性が高い |
栄養成分と健康効果
アスパラガスには、次の栄養成分が多く含まれています。
| 栄養成分 | 健康効果 |
|---|---|
| アスパラギン酸 | エネルギー源となり、疲労回復の効果がある。 |
| ルチン | 生活習慣病を予防する。 |
| 葉酸 | DNAや赤血球をつくる。 |
| β-カロテン | 抗酸化作用があり、皮膚や粘膜の健康維持に役立つ。 |
| ビタミンC | 免疫力を高め、コラーゲンの生成を促進する。 |
| カリウム | ナトリウムを排出し、むくみを予防する。 |
| サポニン | 免疫力を高める |
| 食物繊維 | 便秘の改善。血糖値の抑制。 |
| アントシアニン | 抗酸化作用。目の健康を維持してくれる。 |
アスパラガスには疲労回復効果や生活習慣病を予防する効果があり、健康を意識する人に適しています。
むくみ予防や、肌の健康を維持する効果にも期待できるため、美容意識の高い人にもおすすめの野菜です。
茎にある三角の「はかま」の部分や穂先にも栄養が多く含まれます。
また、種類によって含まれる栄養価が変わるのもアスパラガスの特徴です。
| グリーンアスパラガス | β-カロテンやビタミンが豊富 |
| ホワイトアスパラガス | カリウム・サポニンが豊富 |
| パープルアスパラガス | アントシアニンが豊富 |
ホワイトアスパラガスのみ日光に当てずに育てるため、β-カロテンをほとんど含みません。
旬の時期と味の違い
アスパラガスの旬は、春と夏の年2回です。
| 収穫時期 | 甘み | 香り | |
|---|---|---|---|
| 春アスパラ | 4~6月 | 濃い甘み | 強い |
| 夏アスパラ | 7~9月 | 爽やかな甘み | 弱い |
春アスパラガスは、甘みと香りが強く味が濃いのが特徴です。
夏アスパラは、春アスパラよりも外皮が柔らかく、爽やかな甘みでさっぱりとしています。
アスパラガスの歴史と主な生産地
アスパラガスは南ヨーロッパが原産地とされており、古くから人々に親しまれてきた野菜です。
紀元前2000年頃には、古代ローマやギリシャで栽培されていた考えられています。
日本には江戸時代にオランダから伝わり、食用として本格的に導入されたのは明治時代になってからです。
大正時代には輸出用のホワイトアスパラガスの生産が広がり始めました。
昭和40年代以降になるとグリーンアスパラガスが一般家庭でも広く流通するようになります。
日本国内の主な生産地は、以下の通りです。
- 北海道
- 熊本県
- 佐賀県
- 栃木県
- 長崎県
冷涼な気候かつ、昼夜の寒暖差が大きい北海道と熊本県で多く生産されています。
アスパラガスの育て方
美味しいアスパラガスを育てるには、適切な育て方が重要です。
具体的には、次のポイントを抑えてください。
- 土壌の準備と場所選び
- 水やりの方法
- 肥料の適切な与え方
- 病害虫対策
- 種まきと植え方
- 栽培に必要な資材
- アスパラガスの成長段階に応じたケア
それぞれ順番に説明します。
土壌の準備と場所選び

アスパラガスは次のような土と環境を選ぶことが大切です。
- 水はけの良い場所と土
- 深く広く耕せる場所
- 他の作物の生育に影響が出ない場所
- 日当たりの良い場所
- 土壌の酸度は弱酸性〜中性
根をしっかりと張らせるため、できるだけ深く広く耕せる場所を選びましょう。
土壌は弱酸性〜中性の土が適しているため、植え付けの1週間以上前に苦土石灰を混ぜてpHを調整しておきます。
日当たりの良さも生育に重要なポイントとなるため、日光がしっかり当たる場所を選ぶことも重要です。
水やりの方法
土の表面が乾いたのを確認してから、鉢の底から水が流れ出るくらいたっぷりと水を与えます。
水やりの際は、根元にしっかり届くように行い、葉に直接かからないよう注意しましょう。
葉に水がかかると病気の原因になることもあります。
基本的には、雨や曇りの日を除いて1日1回を目安に水やりを行うのが一般的です。
ただし、夏場の暑い時期は土が乾きやすいため、朝と夕方の2回を目安に水を与え、水不足にならないよう気をつけてください。
肥料の適切な与え方
アスパラガスは、しっかりと栄養を与えないと良質な芽が育ちにくくなります。
植え付け後から10月頃までは、1ヵ月に1回のペースで定期的に追肥を行いましょう。
その後、冬に向けて生育が落ち着く12月頃には、寒肥を施して土の養分を補います。
2年目以降も同じように、越冬後の3月に1回、さらに5月から10月まで月1回の追肥を続けることで、元気な芽を収穫しやすくなります。
病害虫対策
アスパラガスは、一度植えると長く収穫できる野菜のため、病害虫の管理も継続して行う必要があります。
特に注意したいのは茎枯病で、放置すると収穫量の減少につながるため、早めの対策が欠かせません。
防虫ネットを張るなどして、害虫による食害対策を行うのも効果的です。
それぞれの病気の特徴と対策について詳しく解説します。
茎枯病
- 若い茎に褐色の斑点が現れ、黒い粒が発生した後、病変が全体に広がり枯死する。
- 雨による胞子の飛散で畑全体に感染が広がるため注意が必要。
土壌中のカビが原因で発生するため、敷き藁でマルチングを行い、泥はねによる感染を防ぎます。
銅剤による殺菌も予防に効果的です。
病気が発生した場合は、被害を受けた茎を株元から切り取り、畑の外で処分してください。
斑点病
- 主に擬葉に褐色の斑点が生じる。
銅剤を使用すると、病気の発生を抑えるのに役立ちます。
100倍ほどに薄めた酢を葉に散布することで、病気の進行を防ぐ効果が期待できます。
感染した葉は早めに摘み取り、畑の外で適切に処分しましょう。
ヨトウムシ
- ハスモンヨトウなど蛾の一種。幼虫が葉や茎を食害する。
- 8~9月に発生しやすい。
土を耕すときは、幼虫が潜んでいないか注意深く確認しましょう。
幼虫の見逃しもあるため、防虫ネットを活用して虫の侵入を防ぐなど根本対策も重要です。
もし見つけた場合は、速やかに駆除しましょう。
ネギアザミウマ
- 体長1~1.5mmの細長い形をした虫。
- 葉や茎を吸汁し、被害が大きくなると枯死する。
目の細かい(1mm以下)防虫ネットを設置することで、アザミウマの産卵を防ぐことができます。
雑草が生い茂ると発生しやすくなるため、こまめな草取りを心がけましょう。
200~300倍に薄めた酢を散布することで、ある程度の忌避効果が期待できます。
種まきと植え方
アスパラガスは種から育てると収穫まで3年かかるため、早く収穫したい場合は1~2年育苗された大苗から育てましょう。
種まきの時期は3~5月頃で、発芽に適した温度は25~30℃です。
種は10cmの育苗ポットで育てます。
- 種を2~3日水に漬ける
- 5mm程の穴を土にあけ、種を撒く
- 発芽まで用土が乾燥しないように管理する
- 草丈5cmになったら間引きする
- 草丈が10~15cmになったら植え替える
① 種を2~3日水に漬ける
アスパラガスの種子は厚く硬いため、水を吸いにくく発芽に時間がかかるのが特徴です。
種子の表面にすり鉢などで軽く傷をつけ、水に2~3日間漬けて発芽率を高めます。
浸した水は毎日替えることが重要です。
温度管理ができる場合は、25~30℃のぬるま湯に浸すと、さらに発芽しやすくなります。
② 5mm程の穴を土にあけ、種を撒く
直径約10cmのポットに野菜用の培養土を入れ、中央に指で軽く5mmほどの穴をあけます。
そこに種を2~3粒落とし、指先でやさしく土をかぶせましょう。
覆土後は表面を軽く押さえて、土を安定させるのがポイントです。
③ 発芽まで用土が乾燥しないように管理する

種をまいたあとは、たっぷりと水を与え、土の乾燥を防ぐために新聞紙をかぶせて保湿します。
発芽するまでは、そのまま覆った状態を保ちましょう。
保水性の高いバーミキュライトを使うのも一つの方法です。
土の表面に薄くまいてから水を与えることで、適度な湿度を維持しやすくなります。
⑤ 草丈5cmになったら間引きする
草丈が約5cmに成長したら、元気な苗を1本だけ残して間引きを行います。
健康で丈夫な1本を残して、弱い苗は丁寧に抜き取ってください。
間引き後も、適度な水やりを続けることが大切です。
⑥ 草丈が10~15cmになったら植え替える
草丈が10~15cm、本葉が3~4枚まで成長したらプランターや畑へ植え替えのタイミングです。
植え付けに適した時期は5~6月で、順調に成長させるためにも環境を整えておいてください。
プランターを使用する場合は、深さ30cm以上のものを選ぶのが理想的です。
畑に定植する場合は、苦土石灰と化成肥料を植え付け2週間前に混ぜ込みましょう。
大苗(根株)から育てる場合の手順は下記の通りです。
- 10分ほど根に水を吸わせる。
- プランターの半分まで用土を入れる。
- プランターの中心に芽がくるように入れる。
- 芽の上から約5cm土をかける。
- 水をたっぷり与える。
横型プランターの場合は根をできるだけ広げて入れましょう。
通常のプランターや鉢の場合は根をねじりながら入れるのがポイントです。
栽培に必要な資材
アスパラガスの栽培に必要な資材は、以下のとおりです。
- 野菜用培養土
- 鉢底石
- プランター・鉢
- 支柱
- 麻紐、ビニール紐
- 防虫ネット
- 化成肥料
それぞれ順番に解説します。
野菜用培養土
アスパラガスをプランターで育てる場合は、市販の野菜用培養土を使うのがおすすめです。
土の適正な酸度はpH6.0~7.0で、排水性・保水性・通気性のバランスが取れたものを選ぶと、健康に育ちやすくなります。
あらかじめ肥料成分が含まれている培養土を選ぶと、手間がかかりません。
鉢底石
アスパラガスは水はけの良い土壌が必須のため、プランターの底に鉢底石を敷き、排水性を良くします。
底に隙間ができることで、通気性もよくなり、悪い菌の発生や根腐れを防ぎます。
あらかじめネットに入れてから利用すると、土から掘り出す手間が省けるので、再利用の際に便利です。
プランター・鉢
アスパラガスを育てるには、深さ30cm以上のプランターを用意しましょう。
1株だけ植える場合は、10号以上の植木鉢を選ぶと、しっかり根を張らせることができます。
アスパラガスの根は1~2mほど伸びるため、十分な深さのある容器を選ぶことが大切です。
支柱
アスパラガスは風や成長の重みで倒れやすいため、支柱を立てることが欠かせません。
支柱の長さは150cm程度が適しており、しっかりと苗を支えることができます。
素材は耐久性の高い亜鉛メッキ加工のものを選ぶと、長期間使用できて安心です。
麻紐・ポリテープ
支柱に茎を固定する際には、麻紐やビニール紐を使うと便利です。
茎を傷つけないように、緩めに結ぶことが重要で、風で揺れても茎が折れにくくなります。
麻紐は自然分解しやすく、環境に優しい選択肢としておすすめ。
防虫ネット
害虫による被害を抑えるため、目の細かい防虫ネットを張ります。
小さな虫の侵入を防ぐために、目あいは1mm以下のものがおすすめです。
化成肥料
アスパラガスには定期的に肥料を与えることが重要です。
特にプランター栽培では、化成肥料の使用が推奨されています。
チッ素・リン酸・カリウムをバランスよく含んだ肥料を選びましょう。
アスパラガスの成長段階に応じたケア
アスパラガスは種まきから収穫までに3年かかりますが、適切に育てればその後も約10年収穫できる野菜です。
発芽期からの育て方のポイントを説明します。
- 発芽~育苗|土壌を常に湿らせ、温度管理に注意する
- 植え付け後~1年目|定期的な追肥と支柱による倒伏防止
- 冬の休眠期|マルチングをし冬越しする
- 2年目|収穫せずに株を大きくする
- 3年目以降|収穫しすぎない
発芽~育苗|土壌を常に湿らせ、温度管理に注意する
発芽の最適温度は25-30℃です。
気温が15℃を下回ると発芽までに時間がかかり、生育が遅れることがあります。
乾燥に弱いため、種まき後はしっかりと水を与え、ポットの表面に新聞紙をかぶせて乾燥を防ぐのがおすすめです。
発芽後も、地温が低い場合や、高温の場合には生育不良になることがあります。
特に乾燥には注意し、土が乾きすぎないようこまめに水を与えることが大切です。
植え付け後~1年目|定期的な追肥と支柱による倒伏防止
植え付け後から1年目までに必要なケアは次の通りです。
- 5~10月頃まで追肥を月1回行う
- こまめに除草を行う
- 支柱を立て、倒伏を防止する
5月以降は茎がぐんぐん伸びるため、十分な栄養を与えることが大切です。
雑草が増えるとアスパラガスに十分な栄養が行き渡らないため、こまめに草取りを行ってください。
敷き藁でマルチングをすれば、雑草の発生を抑えつつ、土の乾燥防止にも役立ちます。
支柱は150cm程のものを用意し、紐を2~3段に張り、倒伏を防ぎましょう。
冬の休眠期|マルチングをし冬越しする
冬はアスパラガスの休眠期のため、茎や葉が黄色に変わってきたら地際部から5~7cmを刈り取り、できたら焼却処分します。
刈り取った茎は病気にかかっている場合もあるので、残さないよう丁寧に集めて畑の外で処分しましょう。
刈り取り後は、ぼかし肥や米ぬかを追肥して春の成長を助けます。
霜対策も重要で、プランターは室内に移動し、畑ではもみ殻や敷き藁を敷いてマルチングを行い、保温を心がけてください。
2年目|収穫せずに株を大きくする
2年目には細い若芽が生えてきますが、収穫せずにそのまま株を育て、根を太らせましょう。
追肥は、化成肥料やぼかし肥を使用し、3月頃に1回、5月以降に月1回行います。
大苗から育てた場合は2年目から収穫が可能ですが、細い芽は収穫せずに残し、そのまま育ててください。
冬の管理は1年目と同様に行い、霜対策や刈り取りを適切に進めましょう。
3年目以降|収穫しすぎない
3年目になると、いよいよ収穫の時期を迎えます。
収穫しすぎてしまうと翌年以降の収穫量に影響がでるため、太い芽を収穫し、細い芽は根の成長のためにそのまま残しましょう。
収穫が終わる6月頃には、追肥を行い、株の成長を促します。
葉が茂っている間は栄養をしっかり補給することが大切なので、10月頃まで月1回のペースで肥料を与えるのが理想です。
アスパラガスの栽培条件
アスパラガスを栽培する場合、次の条件に配慮しましょう。
- 置き場所と日当たり
- 温度と湿度の管理
- 用土の選び方
- 風通しと支柱設置
それぞれ順に説明します。
置き場所と日当たり

プランター栽培は、日当たりと風通しの良い場所を選びましょう。
日光を浴びることで養分を蓄えるため、できるだけ長く日に当てる必要があります。
ただし、日差しが強すぎる場合は葉焼けを起こすので、遮光ネットなどで日差しを和らげてください。
多湿を嫌うため雨が溜まる場所は避け、休眠期に入る冬にはプランターを室内へ入れます。
温度と湿度の管理

生育適温は15~20℃です。
発芽地温は25~30℃と高めのため、15℃以下だと発芽までに日数がかかります。
気温が5℃を下回ると生育が悪くなりますが、休眠中の地下茎はかなりの低温に耐えることが可能です。
真夏の乾燥に弱いため、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをし、藁などでマルチングをして乾燥を防ぎましょう。
用土の選び方
市販の野菜用培養土を使うと簡単です。
排水性・保水性・通気性に優れた砂土質のものが適しています。
アスパラガスは栄養をたくさん必要とする野菜のため、元肥入りのものを選んでください。
次のものを混ぜ合わせて自作することも可能です。
- 赤玉土(小粒):7
- 腐葉土:2
- バーミキュライト:1
上記の土に苦土石灰と化成肥料を植え付け2週間前に混ぜこみ、酸度を調整しましょう。
風通しと支柱設置
アスパラガスは草丈が1.5mを超え、風や雨で倒れやすいため、支柱設置は必須です。
草丈が60cmを超えたら、四隅に支柱を立て、紐を2~3段張りましょう。
紐を張る位置は、高さ60cmと120cmあたりです。
風通しが悪くなると病気の原因にもなるため、倒伏を防止することで通気性を保ちます。
アスパラガスの開花および収穫時期

アスパラガスの開花時期と収穫時期について説明します。
アスパラガスの開花時期
アスパラガスは5~7月に白やクリーム色の小さな花を咲かせます。
雄株には雄花しか、雌株には雌花しか咲きません。
雌花は咲いた後に実をつけ、その実から種子が落ちると雑草化してしまいます。
収穫に最適な時期の見極め方
アスパラガスは春先に出てくる若芽を収穫します。
芽の長さが15~25cm程になったら収穫可能ですが、穂先が締まっているうちが食べ頃で、芽が育ちすぎ穂先が開いてくると味が落ちてしまいます。
約3週間収穫が可能ですが、芽をすべて採ってしまうと翌年以降の収穫量が減ってしまうので注意しましょう。
夏から秋にかけても収穫したい場合は、春の収穫は早めに終え、追肥を行います。
収穫時期による味の違い
春芽は柔らかく瑞々しい味が特徴です。
根に蓄えられた養分によって育つ春アスパラガスには、強い香りと甘みがあります。
夏芽は、春芽に比べ外皮が柔らかく、味はあっさりと淡泊です。
アスパラガスの芽がでない原因は?
アスパラの芽が出ない原因は次の通りです。
- 肥料が不足している
- 植え付け年数が不足している
- 根に被せる土が多すぎる
- 土壌環境が悪い
- 温度や湿度が不適切
それぞれ順に解説します。
肥料が不足している
アスパラガスは多肥性の野菜のため、肥料が不足していると芽が出ません。
また雑草が生えていると、雑草に栄養を取られてしまい栄養が足りなくなるため、草取りを行い、肥料をしっかり与えてください。
冬場に追肥を行うと、芽が出始める3~4月に効き始めます。
刈り取った茎の中心から20cm離れたところに円を描くように肥料を撒き、土に混ぜこみましょう。
植え付け年数が不足している
アスパラガスは種まきから3年目でようやく収穫できる野菜です。
栄養を貯蔵する太い根から芽が生えてくるため、しっかりと株を育て、太い根を育てる必要があります。
夏と秋に各2回追肥を行い、株を成長させましょう。
被せる土が多すぎる
3年目なのに芽が出ない、または大株を植え付けたのに翌年に芽が出ないという場合は、植え付け時に被せる土が多すぎた可能性があります。
覆土が多かったと感じる場合は、周りから手でほぐし、上の土を減らしてください。
根を傷つけないように優しく手で行うのがポイントです。
種から育てる場合も同様で、深く埋めすぎると発芽しにくいため、種は10mm以下の深さに、浅く撒きましょう。
土壌環境が悪い
アスパラガスの適性酸度は、pH6.0~7.0です。
水はけが悪かったり、土が固すぎたりするだけでなく、土壌酸度が偏っている場合も芽がでません。
畑での栽培は、雨で酸度が弱酸性に偏るため、苦土石灰などで酸度調整を行ってください。
土が固いと通気性や排水性が悪くなるため、固い場合は、深く掘り返し、たい肥など有機質肥料を混ぜ込み、土を柔らかくしましょう。
土は繰り返し使うと固くなるため、プランター栽培の場合は定期的に土を交換することが重要です。
温度や湿度が不適切
発芽気温に適していないと発芽が遅れたりします。
アスパラガスの発芽適温は25~30℃、生育適温は生育適温は20~25℃です。
種から育てる場合、気温が低いと発芽に時間がかかります。
気温が高い時期に多湿になると根腐れを起こし発芽しないため、水の与えすぎに注意しましょう。
アスパラガスの増やし方
アスパラガスの増やし方のポイントは次の4つです。
- 摘心と摘果の方法
- 水耕栽培による増やし方
- 植え替えの適期と手順
- 鉢替えのやり方
それぞれ説明します。
摘心と摘果の方法
通気性を保つために摘心を行い、病気の発生を防ぎます。
アスパラガスは茎が伸びていくと倒れやすくなるため、摘心は重要な作業です。
茎が伸びきって穂先が垂れてきた頃に、地面から130cm程の高さでカットします。
よく切れるハサミで、晴れた日の午前中に行いましょう。
水耕栽培による増やし方
アスパラガスは、茎が高く伸び、また多年生植物のため水耕栽培向きではありません。
アスパラガスを増やしたい場合は、株分けを行いましょう。
株分けを行うことで、根詰まりを防ぎ、収穫量のアップにも期待できます。
株分けに適した時期は冬に茎が枯れた後か、5~6月です。
手順は次の通りです。
- 株を掘り起こす
- 株を2~3つに分割する
- 分割した株を植え付ける
① 株を掘り起こす
株の周りをクワで掘り起こします。
根を傷つけないように、根から離れたところを掘ってください。
プランターや鉢での栽培の場合は、根株を引き抜きます。
② 株を2~3つに分割する
株についた土を振り落とし、大きな塊となった株を手で2~3つに分けます。
その際は根を傷つけないようにしてください。
株が小さすぎたり、細かく分けすぎると成長に影響が出るため注意しましょう。
③ 分割した株を植え付ける
分けた株を畑に植える場合は、株間を40~50cm空けて植え付けてください。
畑に穴をあけ、根を広げて入れたら、土をしっかりと株元に寄せます。
プランター栽培の場合はそれぞれ別のプランターへ植えましょう。
プランターを日陰に移動させ、根付いたころに日の当たる場所へ移動させます。
植え替えの適期と手順

種から育てた場合は、草丈が約10cmまで育ったら畑やプランターに植え替えを行います。
畑に植え付ける場合の手順は次の通りです。
- ポット苗を水に漬ける。
- 畑に苗を植える。
- 土を寄せて馴染ませる。
- たっぷりと水やり。
ポット苗を水に漬ける
植え付けを行う日の朝に、苗を水に漬けます。
ポリポットごと苗を水に沈めて、ポット内の空気が抜けるまで浸しましょう。
水に浸すことで土が崩れにくくなります。
畑に苗を植える
植え付けた苗が周囲の土と同じ高さになるか、5cm程低くなるよう植え付けます。
畝幅は約100~120cm、株間は40cm以上とりましょう。
根鉢を崩さないように苗をポットから優しく外し、穴へ植えます。
土を寄せて馴染ませる
穴に苗を入れたら、苗を周りの土を密着させるように土を寄せ戻します。
その際に覆土しないことがポイントです。
株本の土を軽く押さえて安定させましょう。
たっぷりと水やり
植え付けが完了したら、たっぷりと水を与えてください。
その後は表面の土が乾いたら水やりを行います。
プランターに植え付けを行う場合も、同様に行います。
ポットから外した際に根が黒ずんでいるなら根腐れを起こしているため、そういった苗は植えないようにしましょう。
鉢替えのやり方

プランター栽培の場合は1年に1度、3月頃に鉢替えが必要です。
根詰まりを起こさないように、一回り大きな鉢に鉢替えをするか、株分けをします。
- 鉢から根株を取り出し、古い土を落とす。
- 一回り大きな鉢に新しい土を入れる
- 根鉢は崩さず植え付ける。
鉢から根株を取り出し、古い土を落とす
鉢から根株を取り出します。
掘り起こすときは、根を傷つけないように根から離れたところを掘ってください。
取り出した根株についた古い土を、根株を優しくほぐしながら1/3程度振り落とします。
古い土をある程度残すことで、植え替えによるダメージを軽減させることができます。
一回り大きな鉢に新しい土を入れる
根がしっかり成長できるように、一回り大きな鉢やプランターを用意しましょう。
鉢が大きすぎると土が乾きにくくなり、根腐れや徒長の原因となります。
鉢を大きくしたくない場合は株分けを行ってください。
用意した鉢やプランターの底に鉢底石を敷き、新しい野菜用培養土を入れます。
根鉢は崩さず植え付ける
植え付ける際は、根鉢を崩さないようにします。
根を痛めないようほぐしたりせずに、そのまま植え付けましょう。
根鉢に土を寄せ、軽く押さえて密着させます。
根付くまでは、水やりはしっかりと行ってください。