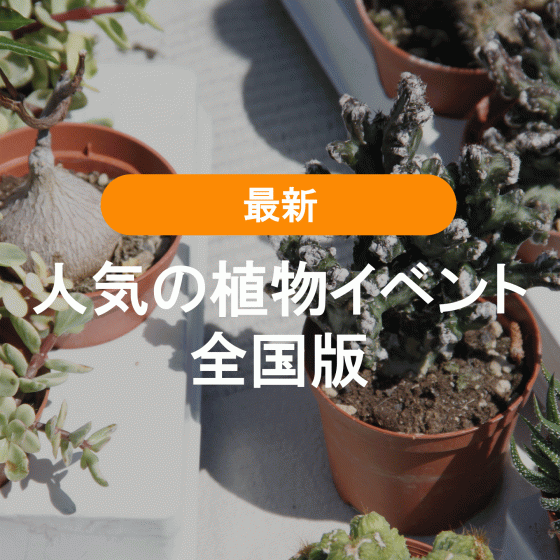古い土を再生させる方法
公開日 2025年09月01日
更新日 2025年12月20日
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

古い土をそのまま使うデメリット

使用済みの古い土は植物の栽培に適していないため、そのまま使い回さないようにしましょう。
なぜなら、古い土はゴミや病害虫などが残っていたり栄養状態が悪かったりするため、植物が育ちにくいからです。
ここでは、古い土を使い回すデメリットについて、詳しく解説していきます。
根っこや雑草が残っている
使用済みの土には、前回育てた植物の根っこや雑草などのゴミも含まれている場合がほとんどです。
土の中にゴミが残ったままだと、以下のように新しい植物の成長を阻害してしまいます。
- 新しい植物の根っこが伸びにくくなる
- 土の栄養分を吸い取られる
- 病原菌に感染しやすくなる
特に、前回育てた植物が「球根」や「宿根草」の場合は、残った根っこが土の中で成長してしまいます。
古い土で新しい植物を育てる場合は、植え付ける前に根っこや雑草などのゴミを除去する作業が必要です。
病害虫が残る
古い土は、病害虫やその卵が残っていたり病原菌に感染していたりする恐れがあります。
その状態の土で植物を育てると、以下のような被害を及ぼす可能性が高くなるでしょう。
- 病害虫によって根っこを食い荒らされる
- 病害虫が増えて他の植物に被害が広がる
- 病原菌に感染する
病害虫被害を防ぐには、植え付ける前に太陽光や熱湯などで土を消毒しなくてはなりません。
排水性が悪くなる
一度でも栽培に使った土は、土の粒が細かく崩れて固くなっているため水はけが悪く、植物を育てるのに適しません。
新しい植物を植える前に土壌改良材を混ぜ込み、排水性や通気性に優れた柔らかい土に再生させる作業が必要です。
土壌酸度や栄養素が偏る
植物を栽培したあとの古い土は、以下のように土壌酸度や栄養素が偏ります。
- 水やりや雨水などによってマグネシウムとカルシウムが流れ出し酸性に傾く
- 土の栄養分が前回育てた植物に吸収されてほとんど残っていない
土壌酸度や栄養素が偏った古い土のまま新しい植物を植えると、根っこから養分を吸収しにくくなり上手く成長できません。
古い土で新しい植物を育てる場合は、土壌改良剤や緩効性肥料を混ぜて、偏った酸度や栄養素を調整しましょう。
簡単!古い土を再生させる方法の手順

古い土は土壌環境が悪く、新しい植物を健康に育てられません。
新しい植物を植え付ける前に、土を再生させる作業が必要です。
ここでは、古い土を簡単に再生させるやり方を紹介します。
熱消毒のやり方は、夏と冬で異なるので時期に適したやり方を選びましょう。
- ゴミと土をふるいで分ける
- 土を熱消毒する
- 水で余分な栄養素を抜く
- リサイクル材を混ぜる
再生作業に必要な道具
古い土の再生作業をする際は、以下の道具を用意しましょう。
- 園芸用ふるい(粗いものと細かいものを用意しておく)
- スコップ
- ビニールシート
- 透明のビニール袋(夏用)
- 厚手のビニール袋(冬用)
- 熱湯
- 水
- じょうろ
- リサイクル材
① ゴミと土をふるいで分ける

古い土には、植物の成長の妨げとなる根っこや雑草などのゴミが残っている場合がほとんどです。
新しい植物を植え付ける前に、ふるいを使ってゴミと土を分けなければなりません。
- 古い土をほぐす
- 粗目のふるいにかける
- 細目のふるいにかける
古い土をほぐす
古い土をビニールシートに広げ、前の植物の根鉢をほぐしながら土を落とします。
大きめの根っこや茎などを取り除いたあと、土を平らに広げて1~2日程度かけて乾燥させてください。
粗目のふるいにかける
続いて、園芸用の粗いふるいにかけましょう。
ふるいで分けられて残った雑草や根っこは、ゴミとして処理してください。
細目のふるいにかける
最後に、園芸用の細かいふるいにかけましょう。
ここでは、ふるいから落ちたパウダー状の土(微塵)をゴミとして処理します。
パウダー状の土が多いと水はけが悪くなるため、しっかり取り除きましょう。
再生対象であるふるいに残った方の土は、必ず捨てずに取っておいてください。
② 土を消毒する

古い土には、新しい植物の成長を阻害する病原菌や病害虫などが残っている場合があり、新しい植物を植える前に、しっかりと消毒することが大切です。
さまざまな消毒方法を、季節や目的に応じて使い分けてください。
石灰窒素や土壌消毒剤を使用するやり方は、環境や人体に悪影響を及ぼす恐れがあるため、できるだけ太陽光や熱湯で消毒しましょう。
太陽光で消毒するやり方
夏は、以下の手順で太陽の熱を使って消毒するのがおすすめです。
日差しが強い7~8月の真夏に行うと良いでしょう。
- ビニールシートに土を広げて全体に水をかける
- 透明のビニール袋に移し替えて口を閉じ、密閉状態にする
- コンクリートの上に置く
- 1~2日おきに上下をひっくり返しながら1~2週間ほど置いておく
黒よりも透明のビニール袋のほうが直接太陽光を当てられ、殺菌効果が高いとされています。
熱湯で消毒するやり方
冬は、以下の手順で熱湯を使って消毒するのがおすすめです。
病原菌や病害虫を完全に死滅させるために、厳しい寒さや霜に当てる必要があります。
寒さの厳しい12~翌2月に行うと良いでしょう。
熱湯を使用する際は、厚手のビニール袋を使用し火傷に注意してください。
- 土をビニール袋に入れる
- 熱湯をまんべんなくかけてかき混ぜる
- ビニール袋の口を閉じて熱を行きわたらせるために1日放置する
- 土を広げて寒風や霜にさらす
- 2~3週間に1回程度上下を入れ替えるようにかき混ぜながら1ヵ月置いておく
石灰窒素で消毒するやり方
古い土は、石灰窒素を散布するだけでも消毒できます。
土に混ぜ込むことで、センチュウや根こぶ病の原因となる病原菌の除去が可能です。
また、石灰窒素は土の中で分解されることによって、窒素やカルシウムが栄養分として残るというメリットもあります。
ただし、石灰窒素は農薬なので、以下に注意して行ってください。
- 素肌が出ないように完全防備する(長袖、長ズボン、マスク、ゴーグルなどを着用する)
- 吸い込む恐れがあるため、風の強い日は散布しない
- アルコールに反応する性質があるため、散布当日は飲酒を避ける
土壌消毒剤で消毒するやり方
土壌消毒剤を散布して古い土を消毒するやり方もあります。
土壌消毒剤は、1回散布するだけで多量の病害虫を死滅させられるのが特徴です。
用途や目的ごとにさまざまな種類があるため、必ず事前に農業資材店や農協の職員に相談してから行ってください。
土壌消毒剤は環境や人体へ悪影響を及ぼす可能性があるため、初心者の方は極力使用を避けましょう。
③ 水で余分な栄養素を抜く

古い土には、余分な栄養素が残っている場合があるため、使い回すと偏った栄養で植物の成長を妨げてしまうかもしれません。
以下の手順に沿って、水で余分な栄養素を抜く作業が必要です。
- 消毒済みの土を空いている鉢に移し替える
- 土に鉢底から流れ出るくらいたっぷりの水をかけて栄養素を洗い流す
- しっかりと乾燥させる
④ リサイクル材を混ぜる|市販のリサイクル材を使用する場合
古い土は、リサイクル材を混ぜることで水はけの良い柔らかな土に再生できます。
リサイクル材は、古い土に適量を混ぜ込めばOKです。
土を再生させるのに適した商品や資材はたくさんあるので、それぞれの特徴を押さえて選ぶと良いでしょう。
市販のリサイクル材のおすすめ一覧
土壌改良に適したリサイクル材は、園芸店やホームセンターなどで購入することが可能です。
市販のリサイクル材は、土の再生を促す資材が複数ブレンドされているので、初心者の方に適しています。
ここでは、おすすめのリサイクル材とそれぞれの特徴を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| おすすめのリサイクル材 | 手軽さ | コスト | 肥料の有無 |
|---|---|---|---|
| 土の栄養剤 観葉植物用 | ◎ | △ | なし |
| 古い土の再生材 | ○ | ◎ | あり |
| 連作障害も軽減する再生材 | ◎ | ◎ | あり |
| 花ごころ 古い土のリサイクル材 | ○ | ○ | あり |
| 食品原料で作った土の再生材 | ○ | ○ | あり |
なお、リサイクル材は商品ごとに規定量が決められているので、取り扱い説明書をよく読んでから使用しましょう。
土の栄養剤 観葉植物用
- 土に撒くだけなので簡単
- 善玉微生物によって土壌環境を改善する
「土の栄養剤 観葉植物用」は、ぼかし堆肥や活性炭、パーライトが配合されたリサイクル材です。
土の表面に約1cmほど撒くだけで、簡単に古い土を再生できます。
石灰由来の土壌改良剤との併用ができないので、注意してください。
古い土の再生材
- 土を柔らかくして通気性や保水性、排水性、保肥力を良くする
- 元肥が配合されているので追肥が不要
「古い土の再生材」は、バーク堆肥やパーライト、ピートモスなどが配合されたリサイクル材です。
粒が崩れて固くなってしまった土に1~2割ほど混ぜ込むだけで、土をフカフカにして通気性や排水性を良くしてくれます。
元肥(緩効性肥料)が含まれているので、混ぜ込んだ後はそのまま植物を育てることが可能です。
連作障害も軽減する再生材
- 土に撒いても混ぜても使用できる
- 活性炭により連作障害を軽減する
「連作障害も軽減する再生材」は、バーク堆肥やパーライト、活性炭などを配合しています。
土の表面に1cmほど撒くだけで、簡単に古い土を再生させることが可能です。
連作障害の原因となる「アレロパシー」という物質を吸着し、連作障害を軽減してくれます。
花ごころ 古い土のリサイクル材
- 土を柔らかくして排水性を良くする
- 土のpHを中性に近づける
「花ごころ 古い土のリサイクル材」は、木質堆肥や牛糞、軽石などを配合するリサイクル材です。
複数の有機質素材に加え、緩効性肥料が含まれているので、混ぜたらすぐに新しい植物を育てられます。
古い土4:本品1の割合で混ぜるだけで、簡単に土を再生させることが可能です。
食品原料で作った土の再生材
- 含まれる素材のすべてが有機物でつくられている
- 発根が良くなる肥料も配合されている
「食品原料で作った土の再生材」は、コーヒーメーカーから仕入れたコーヒー粕に加え、もみがらや有機肥料が配合されています。
堆肥を使用していないため、ニオイが気になりにくいのが特徴です。
土に混ぜ込むだけで、簡単に古い土を再生できます。
④ リサイクル材を混ぜる|資材を自分でブレンドする場合

古い土を再生させるためには、土壌改良に適した資材の特徴を押さえ、自分でブレンドして混ぜ込むことも可能です。
腐葉土(もしくは牛糞)4:赤玉土6の割合で配合したものを土と同量混ぜ込むのが最も簡単で、一般的によく使われます。
自分でブレンドすることで、土の状態によって混ぜ込む資材を調整することが可能です。
一方で、資材ごとに購入する手間だけでなく専門的な知識も要するので、初心者の方には難しいかもしれません。
自分でブレンドする場合に使える資材一覧
| 資材の分類 | 排水性の改善 | 肥料成分の量 | 病原菌の防除 |
|---|---|---|---|
| 植物由来のもの | ○ | △ | △ |
| 動物由来のもの | ○ | ◎ | ○ |
| 鉱物由来のもの | ○ | × | ○ |
| 石灰由来のもの | ○ | ○ | ◎ |
ここからは、土壌改良に適した資材とその特徴を紹介するので、参考にしてください。
植物由来のもの
植物由来の土壌改良剤には、腐葉土やバーク堆肥、ピートモス、もみ殻くん炭などがあります。
古く固くなった土を柔らかくして、通気性や排水性、保水性を改善させることが可能です。
植物の成長に必要不可欠な窒素やリン酸、カリウムなどの肥料成分は含まれていません。
動物由来のもの
動物由来の土壌改良剤には、牛糞堆肥や鶏糞堆肥、豚糞堆肥などがあります。
肥料成分が多く、窒素やリン酸、カリウムなどをたくさん含んでいるのが特徴です。
鶏糞堆肥は化成肥料と同じくらいの栄養素を含むため、多用すると植物の生育不良を引き起こします。
鉱物由来のもの
鉱物由来の土壌改良剤は、バーミキュライトやゼオライト、パーライトなどです。
土に混ぜ込むだけで、通気性や保水性、排水性の改善が期待できるでしょう。
また、無菌の資材が原料となっているので、育苗用土としても使用できます。
石灰由来のもの
石灰由来の土壌改良剤は、生石灰や消石灰、苦土石灰などです。
土に混ぜ込むだけで、通気性や排水性の改善が期待できます。
また、石灰は土のpHバランスを調整してくれるので、土の中に潜む病原菌や病害虫の防除にも効果的です。
もっと簡単に土を再生させるやり方

古い土を再生させるには、手間が少なく短時間でできるやり方もあります。
ここからは、より簡単に古い土を再生させるやり方を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 根っこや雑草を手で取りのぞく
- プランターのまま日光に当てる
- 土に撒くだけの再生材を使う
根っこや雑草を手で取りのぞく
古い土に残った根っこや雑草は、前の植物を撤収させるときに取り除いておきましょう。
このタイミングで取り除くことで、土をふるいにかける手間が不要になります。
プランターのまま日光に当てる
古い土をプランターに入れたまま、太陽光に当てて消毒しながら乾かしましょう。
風が強い日や雨の日は、上からビニールシートをかぶせてあげると安心です。
病原菌が発生した植物を育てた土の場合は、日光に当てながら1年くらい放置することでしっかりと消毒できます。
土に撒くだけの再生材を使う
古い土がしっかりと乾いたら、規定量の再生材を土に撒きましょう。
撒くだけのリサイクル材以外にも、腐葉土やバーク堆肥の土壌改良剤をブレンドさせて土に混ぜ込む方法もあります。
しかし、自分でブレンドする場合は手間と知識を要するので、初心者の方は撒くだけでOKな市販のリサイクル材が良いでしょう。
古い土に関するよくある質問

ここからは、古い土に関してよくある質問をまとめています。
古い土の再生や処分をする前に知っておいたほうが良い内容をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
古い土の再生に適した時期はいつ?
古い土を再生するのに決まった時期はありませんが、以下のように厳しい気候の時期に行うことで、土が再生しやすくなるとされています。
- 日差しの強い真夏(7~8月ごろ)
- 寒さが厳しい真冬(12~翌2月ごろ)
真夏は強い太陽光に、真冬は厳しい寒さや霜によって、土の中に潜む病原菌や病害虫も死滅しやすくなるでしょう。
雨が降ったりジメジメしたりする梅雨の時期は、土が湿って消毒しにくくなるので避けるのが無難です。
土を処分する時はどうしたらいい?
古い土を性分したい場合は、以下の方法を参考にしてください。
- 自宅の庭にまく
- 土の引き取りサービスをしている店舗に持っていく
- ゴミに出す(各自治体のルールに従う)
- 資源物回収業者や不用品回収業者に依頼する
古い土を近所の公園や山などに捨てた場合、不法投棄の対象となり罰せられます。
少量であっても、必ず正しい方法で処分しましょう。
再生させる時に肥料は混ぜた方が良い?
古い土は前作の植物によって栄養分が失われている状態なので、新しい植物を育てる前に肥料を混ぜて栄養分を補う必要があります。
古い土で新しい植物を育てる場合は、植え付ける1~2週間前に緩効性肥料を混ぜ込んでください。
古い土は捨てないで!エコに植物を育てよう
本記事では、古い土をそのまま使うデメリットと、簡単に古い土を再生させる方法について紹介しました。
古い土は処分しにくいだけでなく、廃棄することで環境にも悪影響を及ぼしてしまいます。
古い土の再利用はエコ活動の一環となるので、本記事を参考にしながら土を再生して新しい植物を育ててみてくださいね。