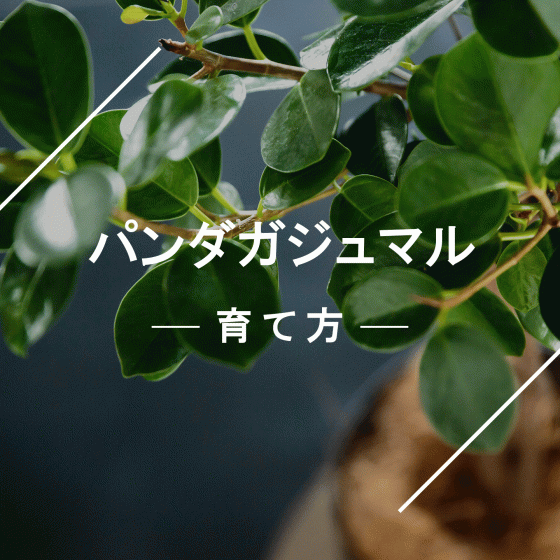イチゴの育て方
公開日 2025年03月24日
更新日 2025年04月22日
育てやすさ
育て方の難易度は普通レベルです。
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。
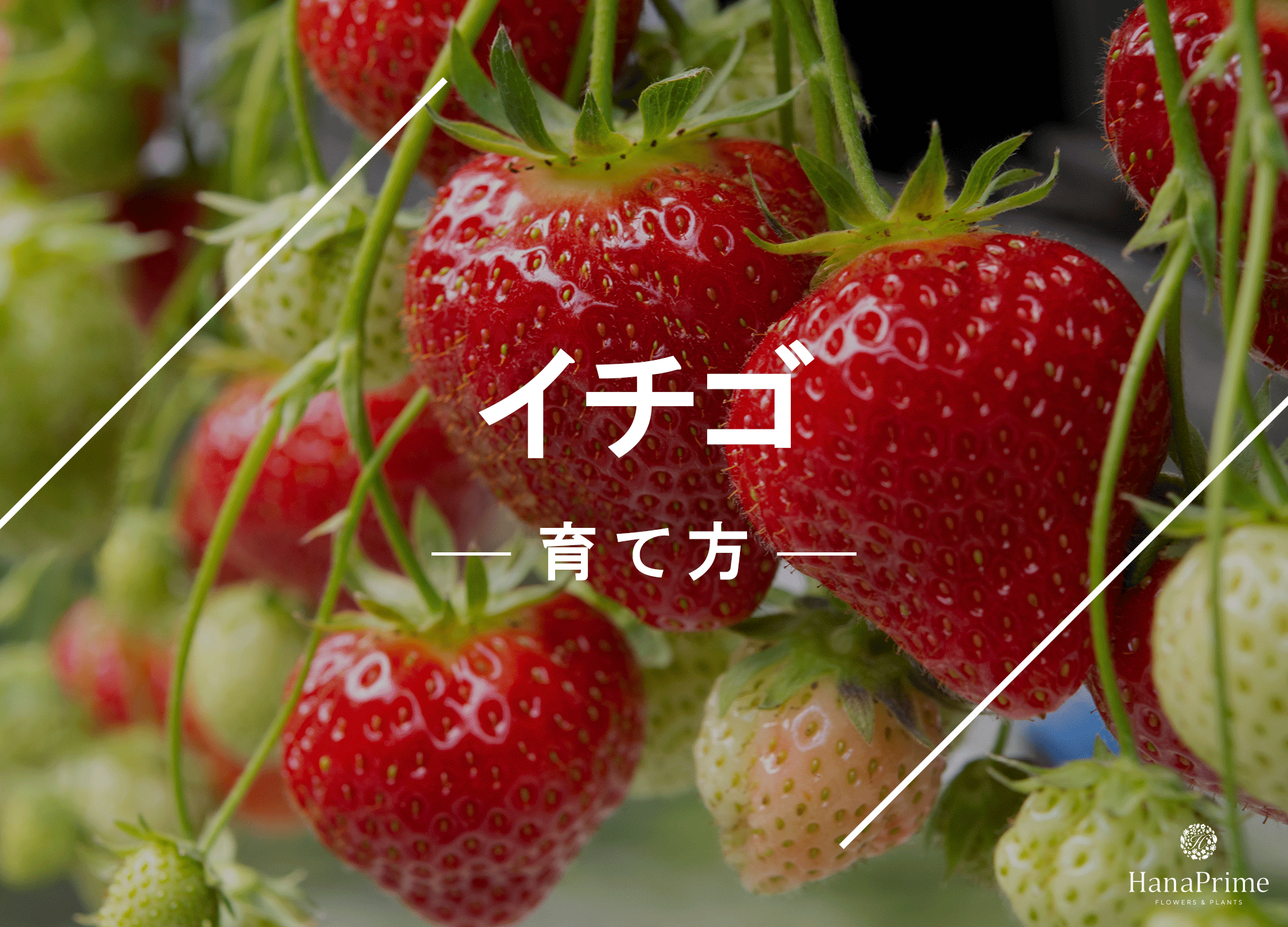
イチゴの基本情報
| 植物名 | イチゴ |
| 学名 | Fragaria |
| 和名 | イチゴ |
| 英名 | Strawberry |
| 別名 | オランダイチゴ、ワイルドストロベリー |
| 原産地 | 南北アメリカ |
| 科名 | バラ科 |
| 属名 | オランダイチゴ属 |
| 開花時期 | 3月~5月頃 |
イチゴはバラ科の多年草で、草本性です。
そのため、野菜として分類されますが、生活感覚では果物として摂取されているため、果実的野菜とも呼ばれています。
イチゴの表面にあるつぶつぶは種ではなく、ひとつひとつが果実で、一粒に200個以上の果実が集まった集合果です。
イチゴの花の開花時期は、品種や栽培方法、地域によって異なりますが、露地栽培の場合は春に開花して5月頃に収穫できます。
しかし、ハウス栽培が普及している日本では、冬~春の収穫を目的に秋から花を咲かせる管理が一般的です。
月別栽培カレンダー
種まき
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
植え付け・植え替え
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
肥料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
開花
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
種類と品種

イチゴの品種は、全世界のうち半分以上が日本のものと言われていて、なんと300種類以上が栽培中です。
日本各地でたくさんの品種改良が行われているため、続々と新しい品種が生み出されていますが、今回は一般的な品種を紹介します。
| 品種 | 大きさ(㎝) | 甘味 | 味の濃さ | フルーティ | 酸味 | さっぱり感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あまおう | 3.5~4.5 | ◎ | ◎ | 〇 | 弱い | なし |
| とちおとめ | 3.0~4.0 | 〇 | ◎ | 〇 | 強い | 普通 |
| 紅ほっぺ | 3.0~4.0 | 〇 | ◎ | ◎ | 強い | なし |
| さがほのか | 3.0~3.5 | ◎ | 〇 | 〇 | 弱い | 普通 |
| ゆめのか | 3.0~4.0 | 〇 | ◎ | 〇 | 普通 | 普通 |
| おいCベリー | 2.5~3.5 | ◎ | ◎ | 〇 | 弱い | 普通 |
| あきひめ | 3.0~4.0 | ◎ | 〇 | 〇 | 弱い | あり |
あまおうは、甘味が強くイチゴの品種の中でもっとも知名度があります。
また、あきひめやさがほのかは酸味が弱くて後味がさっぱりです。
紅ほっぺやとちおとめ、ゆめのかはフルーティな香りが強く、食べたときの満足感があるでしょう。
そして、おいCベリーは小粒ではありますが、甘味が強く生食に適しています。
イチゴは、品種によって、特徴が異なるため、用途や味わいに合わせて選択すると良いでしょう。
栄養成分と健康効果
イチゴの基本的な栄養成分と健康効果は、以下の通りです。
| 栄養成分 | 健康効果 |
| ビタミンC | 肌トラブルに有効、風邪予防 |
| 葉酸 | 赤血球の生成を助ける、胎児の発育をサポート |
| アントシアニン | 目の働きを高める、眼精疲労を予防 |
| 食物繊維 | 腸内環境改善、便秘解消 |
| カリウム | 血圧調整、むくみ予防 |
| エネルギー | 低カロリーでダイエット向き |
イチゴは甘くて美味しいだけでなく、免疫力向上や美肌効果などアンチエイジングや美容意識が高い人にぴったりです。
そして、ビタミンCは、みかんやグレープフルーツの約2倍ほど含まれているため、効率良くビタミンを摂取できるでしょう。
また、生活習慣病予防や貧血予防、疲労回復や腸内環境改善など様々な面から心身ともに健康になるサポートをしてくれます。
イチゴは、身体に必要な栄養素を多く含む果実的野菜で、健康維持に欠かせません。
旬の時期と味の違い

イチゴの旬の時期と味の違いを以下にまとめました。
| 栽培方法 | 旬 | 特徴 |
|---|---|---|
| ハウス栽培 | 12月~5月 | 甘みが強い |
| 露地栽培 | 4月~6月 | 酸味と甘みがバランス良い |
| 夏秋イチゴ | 7月~10月 | さっぱりとした味わい |
イチゴの旬は、栽培方法によって時期が異なり、ハウス栽培の場合は12月頃から春にピークを迎え、一番流通量が多いです。
また、露地栽培の場合は4月〜6月が旬で太陽を浴びて育つため香りが良いでしょう。
そして、冷涼な高地で栽培される夏秋イチゴは7月〜10月がピークとなります。
旬のイチゴはとても美味しくて、栄養価も高いため、時期に合わせて味わうのがおすすめです。
イチゴの歴史と主な生産地
イチゴは、オランダ船によって持ち込まれたのが最初で、日本で食べられるようになったのは江戸時代末期の1830年代と言われています。
その後、欧米から様々な苗が持ち込まれるようになり、明治時代に農業が近代化されると同時に1900年頃には営利栽培が始まっていました。
現在の主な生産地は中国・アメリカ・トルコ、日本では栃木・福岡・熊本などです。
地域ごとに特徴のある品種が多く、それぞれの産地で独自のブランド化が進められています。
そのため、スーパーや産地直送などで、地域の特徴を味わうのも楽しみのひとつです。
イチゴの育て方
イチゴを上手に美味しく育てるためには、適切な管理が重要です。
- 土壌の準備と場所選び
- 水やりの方法
- 肥料の適切な与え方
- 病害虫対策
- 種まきと植え方
- 栽培に必要な資材
- イチゴの成長段階に応じたケア
上記のポイントに分けて、解説します。
土壌の準備と場所選び
イチゴ栽培には、適切な場所選びと土壌作りが欠かせません。
以下にポイントをまとめました。
- 日当たりや風通しが良い環境を作る
- 水はけと通気性が良い場所を用意する
- やや酸性~中性の土壌を用意し、適宜石灰を加えて調整
- 腐葉土、堆肥などを混ぜ込み、肥沃で柔らかい土を作る
- 雑草や病原菌の発生を防ぐため、太陽熱や土壌消毒剤を利用
イチゴは、水はけが良く、適度な保水性がある肥沃な土壌を好み、日当たりや風通しが良い環境で育ちます。
イチゴは根が浅いため、土壌と場所の条件を丁寧に整えることで、病気を予防し、収穫量を増やすことができるでしょう。
畑で栽培する場合は、広い範囲を耕して畝を作ることが大切です。
また、プランターや鉢の場合は市販の野菜用培養土やイチゴ専用培養土を使用すると良いでしょう。
水やりの方法
イチゴの水やりの方法は、以下の通りです。
- 植え付けから活着まで毎日朝夕の水やりが必要
- 活着後は葉水がなくなってから水やりをする
- 収穫期は週2~3回を目安に実施
- 収穫後水やりは控えめにし土が乾かないように保つ
活着とは、根がしっかりと伸びて土の水分を十分に吸い上げられる状態のこと。
葉水があるうちに水やりをしてしまうと、生育が遅くなってしまう可能性があるため注意をしましょう。
また、過剰の水やりは根腐れの原因になりますが、土が湿り気を保つ程度が理想なため適宜様子を観察しながら水やりすることが大切です。
肥料の適切な与え方

イチゴを大きく甘く育てるためには、肥料を適切に与えることが重要です。
畑で栽培する場合は、植え付けの2週間前に施すことが必要で、腐葉土、堆肥、バーク堆肥などを混ぜ込み土壌を馴染ませて寝かせます。
そして、苗の植え付けの2~3週間後に肥料を少量与え、花が咲き始めるとリン酸とカリウムが豊富な肥料を与えましょう。
そして、実が膨らみだしたら収穫期まで1~2週間に1回追肥をすることで、より立派なイチゴを栽培できます。
プランター栽培の場合は、市販の培養土に元々含まれている場合が多いので基肥の追加は不要ですが、追肥は畑で栽培すると同様に必要です。
病害虫対策
イチゴは病害虫に弱いため、適切な対策を行うことで健康な株を保ち、質の良い果実を収穫できます。
ここでは、主な病害虫と対策をまとめました。
ナメクジ
- 夜行性で湿気を好む
- イチゴ果実を食害する
- 被害部に粘液を残す
ナメクジ対策には、水はけを改善し湿度を抑えることが重要です。
また、マルチシートを活用すれば、様々な虫を防ぐことができます。
さらに、専用の誘引剤や駆除剤を使用して被害を軽減しましょう。
アブラムシ
- 茎や葉に群がる
- 汁を吸い加害する
アブラムシ対策には、防風壁を作ることが大切です。
また、反射光を嫌う性質を利用し株元にシルバーマルチを敷くと防ぐことができます。
さらに、黄色に誘引される特徴を生かして粘着板や粘着テープを株の周囲に設置しましょう。
ハスモンヨトウ
- 芽、つぼみ、果実を食害する
ハスモンヨトウ対策には、防虫ネットや寒冷紗でトンネル掛けをします。
また、葉裏に卵を見つけたら潰すことで、事前に防ぐことができるでしょう。
そして、黄色を嫌う性質を利用し、周囲にマリーゴールドを育てるのもひとつです。
種まきと植え方
イチゴは種からも育てられますが、発芽に時間がかかるため苗から育てるよりも難易度が高いため、観賞用や珍しい品種を育てる際に適しています。
イチゴは、以下の手順で種まきと植え付けを行いましょう。
- 種の冷蔵処理をする
- 土壌を準備し、種をまいて管理する
- 発芽後の管理の実施
- 苗の植え付け
それぞれ順番に解説します。
① 種の冷蔵処理をする
イチゴの種は発芽率を上げるため、低温処理を行います。
イチゴの種を湿らせたティッシュや脱脂綿に包み、ビニール袋に入れて冷蔵庫のチルド室で3日間ほど保管しましょう。
寒さから解放されたイチゴの種は、春だと思い込み発芽の準備をはじめ、10日前後で発芽します。
② 土壌を準備し、種をまいて管理する
種まき用の培養土をセルトレイやポットに入れ、種を1粒ずつ表面に置き、軽く押し付けます。
イチゴの種は光が発芽を促進する好光性種子のため、土を覆う必要はありません。
種まき後は、透明なビニール袋やカバーで覆い湿度を保ちつつ、直射日光は避けましょう。
③ 発芽後の管理の実施
発芽したらカバーを外し、日の当たる場所に移し、土が乾燥しすぎないように注意して水やりを実施します。
発芽初期で気を付けなければいけないことは、いちごに触らないということ。
いちごの根は、繊細でとても傷がつきやすく、土の表面近くに根を張るため、触ってしまうとすぐに枯れてしまいます。
④ 苗の植え付け
いちごの苗を枯らさずに植え付ける方法は、丈夫な根とたくさんの葉が育っている時です。
イチゴの苗は、クラウンが埋まると腐る可能性があるため、土に埋まらないよう注意して、植え付けましょう。
植え付け後は、たっぷりと水を与えながら、適宜肥料を与え、根が土に密着するような関わりが大事です。
栽培に必要な資材
イチゴの栽培に必要な資材は、以下の通りです。
- イチゴの苗
- 水
- プランター、植木鉢
- 軽石
- じょうろ
- 移植ゴテ
- 肥料
- 土壌消毒剤
- 土
夏や秋になると、ホームセンターでイチゴの苗を購入することができるため、なるべく葉が大きい物を選ぶようにすると立派に育ちます。
育てたい場所や品種によって必要な肥料や資材などが異なってくるため、臨機応変に対応しましょう。
イチゴの成長段階に応じたケア
イチゴの成長段階に応じたケアは、美味しく水分たっぷりの果実を育てるのに欠かせません。
イチゴの苗を購入して栽培する場合、成長段階に応じたケアは以下の通りです。
- 初期成長期:適切な温度と湿度の管理
- 成長期:葉や茎の成長を促すポイント
- 開花期:受粉をしっかりさせる
- 果実形成期:果実をしっかり赤くするコツ
- 収穫期:果実を傷つけないためには
① 初期成長期:適切な温度と湿度の管理
いちごの生育適温は、気温約20~25℃で地温約18~22℃です。
きちんと温度を管理することで初期成長を促せます。
苗の植え付け直後は、根が土壌に定着するまで十分な水やりが必要です。
また、土が乾きすぎないように、湿り気を保つ程度に水を与えましょう。
ただし、過湿は根腐れを引き起こすため避けます。
② 成長期:葉や茎の成長を促すポイント
成長期には、葉や茎の成長を促すため肥料をしっかりと与えることが大切です。
様々な成分の中でも窒素分の多い肥料を少量与えることで、より成長を促すことができます。
また、風通しを良くするために古い葉や小さなランナーを間引きして管理することが大切です。
③ 開花期:受粉をしっかりさせる
開花期には、のちの果実にも影響してくるため、受粉をしっかりさせることが重要です。
屋外栽培の場合は自然に受粉しますが、室内や温室では人工授粉を補助すると効果的。
綿棒や小さな筆で花の中央を優しく撫でることで受粉を助けます。
また、開花期には窒素だけでなくリン酸とカリウムが豊富な肥料を追加して、開花と果実形成を促しましょう。
④ 果実形成期:果実を赤く大きくするコツ
果実形成期では、果実を大きくするために十分な水やりが必要です。
果実に直接水をかけてしまうと育成を遮る可能性があるため、かからないよう注意しながら、適量を保ちます。
そして、果実が赤くなるまで、肥料を数回に分けて与える追肥を行いましょう。
⑤ 収穫期:果実を傷つけないためには
いよいよ開花から4~6週間後に、果実が完全に赤く熟したら収穫です。
収穫する際に、果実を傷つけないために茎を少し残してハサミで切ります。
また、収穫をしながら傷んだ果実や病気の兆候がある部分を取り除くことで、株全体の栄養状態を保つことができるでしょう。
収穫した果実は、すぐに冷蔵庫に入れると新鮮な状態を保つことができ、水洗いは保存前ではなく、食べる直前に行うと傷みを防げます。
イチゴの栽培条件
イチゴを栽培するためには、条件があります。
- 置き場所と日当たり
- 温度と湿度の管理
- 用土の選び方
- 風通しと支柱設置
それぞれ順番に解説します。
置き場所と日当たり

イチゴは日当たりを好み、1日6〜8時間以上の日光が必要なため、午前中から日中にかけて、しっかり光が当たる場所を選びます。
しかし、真夏の直射日光では痛んでしまう可能性があるため、秋から春は日当たりの良い場所で管理が必要です。
また、夏夏は半日陰になる場所に置きましょう。
イチゴは、風通しがよく水はけの良い場所を好み、水はけが悪いと根腐れの原因になるため注意が必要です。
プランターや畑などで栽培する場合、イチゴは冷涼な気候の中で著しく成長し、暑さや乾燥を嫌うため、夏越の心配がない秋植えがおすすめ。
温度と湿度の管理
イチゴの育成温度は、品種によって異なりますが、日中約20〜25℃、夜間約10〜15℃が理想的な温度です。
夜間の冷え込みが予想される場合は、ヒートポンプ暖房装置を用いて防寒対策をしましょう。
また、高温状態の時は、遮光ネットを用いたり、日陰に移動をしたりして管理が必要です。
また、イチゴの栽培に適した湿度は約50〜70%なため、湿度が低い場合は水やりをして管理をし、高い場合は換気扇や窓を開けて管理が欠かせません。
湿度が高すぎてしまうと果実や花が腐敗する原因になり、低すぎてしまうとカビやダニ発生の要因になるため、適切な湿度管理が大切です。
用土の選び方

イチゴを地植えで栽培する場合は、同じ場所で何度も栽培すると土壌が疲弊し、病害のリスクが高まります。
そのため、イチゴの栽培場所を毎年変えるか、輪作を取り入れると良いです。
輪作とは、一定の期間、同じ場所において種類の違う作物を栽培すること。
また、美味しいイチゴを育てるためには土壌のリフレッシュが必要不可欠です。
そのため、プランターで栽培する場合は、新しい土壌を用いたり、地植えの場合は、太陽熱消毒や石灰窒素を利用して消毒したりしましょう。
風通しと支柱設置

イチゴ栽培では、風通しの良さが美味しくて立派な果実を育てるのにとても重要です。
風がしっかりと通ると病害虫の予防になったり、葉や茎の成長につながったりします。
また、イチゴの栽培で支柱を設置すると、果実が地面に触れるのを防ぎ、病害を減らすと同時に果実の品質を向上させるために重要です。
以下に、支柱の設置方法や特徴をまとめました。
| 支柱の種類 | 特徴 |
| アーチ型支柱 | 果実が地面に触れるのを防ぎ、作業性が良い |
| 1本支柱 | 小規模栽培向きで、各株を個別に支えるため管理がしやすい |
| 棚式支柱 | 地植え・鉢植えの両方で活用可能で、果実が均一に成長しやすい |
| 三角形支柱 | 安定性が高く、風にも強い |
| 垂直ネット支柱 | 小スペースで栽培可能、縦方向に伸ばすことで収穫がしやすい |
| クロス支柱 | 簡単に設置可能で、果実が地面に触れるのを防ぐ |
上記を参考にして、イチゴの育てたい場所や規模感などに合わせて、支柱設置を行いましょう。
イチゴの開花および収穫時期
イチゴの開花および収穫時期について、解説します。
- イチゴの開花時期
- 収穫に最適な時期の見極め方
- 収穫時期による味の違い
ひとつずつ説明します。
イチゴの開花時期
品種によって開花時期は前後することはありますが、3月〜5月頃に小さくて白いお花を咲かせます。
イチゴの花は自家受粉しますが、風通しや昆虫の活動が少ない場合、毛の細かいブラシや耳かきを用いて人工的に受粉させましょう。
受粉に失敗してしまうと、奇形果の原因になるためきちんと受粉させることが大切です。
また、奇形果は他の果実の肥大に影響するため小さいうちに摘み取りましょう。
収穫に最適な時期の見極め方

いちごの収穫時期は、開花してから低温期は40日〜60日、高温期は25日〜30日で適期になります。
果実全体が鮮やかな赤色に染まり、甘い香りが強く漂う物から次々に収穫しましょう。
また、ヘタが青々として元気な状態の物が良い収穫時期を表しており、軽く触ってみて程よく弾力があり、柔らかすぎない状態が理想的。
果実は、傷ついてしまうと傷みが早くなってしまうので、優しく持ちながらハサミを用いてヘタの近くを切り、丁寧に収穫します。
収穫時期による味の違い
イチゴは、大きく分けてハウス栽培(12月〜5月)と露地栽培(4月〜6月)と夏秋イチゴ(7月〜10月)があり、収穫時期が異なるため味も違いがあります。
以下に、違いを表でまとめました。
| 特徴 | ハウス栽培 | 露地栽培 | 夏秋イチゴ |
|---|---|---|---|
| 甘味 | ◎ | 〇 | △ |
| 味の濃さ | ◎ | ◎ | 〇 |
| フルーティ | 〇 | ◎ | △ |
| 酸味 | なし | 普通 | 強い |
| さっぱり感 | なし | 普通 | あり |
栽培方法による収穫時期の違いによって、四季折々の味を感じられるでしょう。
ハウス栽培は、温度や湿度が管理されているため、味が安定していて、全体的に濃厚でジューシーな風味が特徴です。
また、露地栽培は、自然環境で育つため、季節や天候によって風味が変化しますが、全体的に甘味と酸味のバランスが良く、濃厚でフルーティな味わいがします。
そして、夏秋イチゴは暑い時期に収穫されるためさっぱりした味わいが特徴で、加工にも適しているでしょう。
同じイチゴでも、料理の用途や味わいたい風味によって、栽培方法を考えてみてはいかがでしょうか。
イチゴの実がならない原因は?
イチゴの実がならない原因を以下に分けて、解説します。
- 肥料の与えすぎ
- 日当たりが不足している
- 着果不振
- 栄養不足
- 温度や湿度が不適切
ひとつずつ説明します。
肥料の与えすぎ
肥料の与えすぎは、葉や茎を成長させることにエネルギーを使うため、花芽の形成が抑えられ、実がつきにくいです。
また、過剰な肥料は植物を弱らせ、病害虫に対する抵抗力を低下させます。
そして、葉が茂りすぎることで通気性が悪化し、カビといった病気が発生しやすくなるでしょう。
肥料を与えすぎた場合は、水で土を十分に洗い流すと、余分な肥料成分を除去できます。
しかし、水を与えすぎることで腐る可能性もあるため、注意が必要です。
また、次の施肥を控え、株の状態を観察しましょう。
日当たりが不足している
イチゴが健康に実をつけるためには、一般的に1日6~8時間以上の直射日光が必要です。
日当たりが不足していると、光合成不足により成長に必要なエネルギーを作り出せません。
そのため、葉や茎、花芽の発育が遅れてしまい、花が少なくなり実がつかなくなります。
日当たり不足を防ぐために、適切な植え付け場所の選定や株の間隔調整などの管理を行いましょう。
また、光量が不足している場合には人工照明や反射材を活用することで、栽培環境を改善できます。
着果不振
着果不振とは、花同士が上手に受粉できず実を結べないことであり、原因は、以下の通り様々です。
- 寒い季節や悪天候などにより昆虫の活動が少ない
- 温度や湿度の不適合
- 葉や茎ばかりが育ち、花芽の形成が抑制
- 花や果実の形成に必要な栄養が足りない
- 花の管理不足
- 不足や過剰な水やりによる根のダメージ
着果不振を予防するためには、育てる環境を整え、定期的な観察と共に自然受粉が難しい場合は、人工授粉を定期的に行う必要があります。
栄養不足
栄養不足の状態だと、樹全体に栄養が行き届かずに実がならない原因となります。
栄養不足の原因は、以下の通りです。
- 不適切な施肥
- 土壌中の有機物や栄養素が不足している
- 水分不足や過剰
- 病害虫や過湿で根が傷むと、栄養吸収能力が低下する
栄養不足は、きちんと対策を実施することで防ぐことができ、適切な施肥を行い、土壌の改良や適切な水分管理をしましょう。
そして、葉の色や成長具合を観察し、異常があれば早めに施肥や剪定を行います。
温度や湿度が不適切
イチゴは、夜間の温度が10〜15℃、昼間の温度が20〜25℃程度の環境を好みます。
温度が低すぎると、花芽の発達が遅れたり、結実に必要なホルモンの生成が減少したりするため、実がつかなくなることがあるでしょう。
また、温度が高すぎると、花粉の活力が低下し、受粉がうまくいかないことが多く、植物全体がストレスを受け、果実の発育が阻害されます。
そして、イチゴに適した湿度は、50〜70%です。
湿度が低すぎると、受粉が失敗する可能性があり、高すぎると、花粉が粘着性をもち、受粉が不十分になることがあります。
適切な温度や湿度を維持することが、イチゴの結実率を上げる大切なポイントです。
イチゴの増やし方
イチゴの増やし方のポイントは、以下の通りです。
ひとつずつ紹介します。
摘心と摘果の方法
摘心とは、植物の生長点を切り取る作業です。
イチゴは、実をつけ始める前にランナーと言われる細い茎や脇芽が伸びてきますが、放置していると茂りすぎてしまいます。
そのため、親株の負担を軽減するために必要な数だけ残して他を切りましょう。
次に、摘果とは、余分だったり未熟だったりする果実を間引くことです。
一次花房以外に咲く花や果実は、早い段階で摘み取り、病気や形の悪い果実は、見つけ次第取り除きましょう。
株全体の栄養を少ない果実に集中させ、果実の大きさや甘さを向上させます。
綺麗な植物に手を入れることに抵抗感があるかもしれませんが、摘心と摘果をバランスよく行うことで立派なイチゴを育てる手助けになること間違いありません。
挿し木によるイチゴの増やし方
挿し木とは、親株の茎や葉の一部を使って新しい株を育てる方法です。
イチゴの挿し木による増やし方の手順をまとめました。
- 挿し穂の準備
- 挿し木を植える
- 発根を促す環境作り
- 植え替え
① 挿し穂の準備
若くて健康な茎を選び、約5〜8cmの長さに切り取り、下部の葉を2〜3枚程度残して、それより下の葉はすべて取り除きます。
もし葉が大きすぎる場合は、蒸散を防ぐために葉を半分の大きさにカットしましょう。
② 挿し木を植える
挿し穂の下端を土に約2〜3cm挿し込み、土を軽く押さえて固定します。
挿し木の土として適しているのは、水はけが良く適度な湿度を保てるものです。
③ 発根を促す環境作り
挿し木を植えた容器を半日陰の場所に置き、直接の強い日差しを避けましょう。
土が乾燥しないように、毎日軽く水やりが必要ですが、水のやりすぎによる過湿に注意してください。
高い湿度を保つために、透明なビニール袋やカバーをかぶせるのも効果的です。
④ 植え替え
挿し木から2〜3週間後、軽く引っ張って抵抗を感じたら根が出ている証拠です。
発根したら、ポットや畑に植え替えて、適度な水やりと日光を管理をします。
水耕栽培による増やし方
イチゴは水耕栽培によって、育てることができ、生産数を増やせる可能性があります。
水耕栽培とは、土を使わずに植物の根っこ部分を水溶液につけると、直接栄養をあたえられるため、手軽に土を使わずに育てることができる方法です。
手順は、子株を養液にセットすると、2週間前後で発根するため、根が十分に伸びたら独立した栽培容器に植え替えます。
水耕栽培の初心者は、水耕栽培専用キットの購入がおすすめです。
植え替えの適期と手順
イチゴの植え替えは、春植えの場合は3月〜4月頃、秋植えの場合は9月〜10月頃が適期とされています。
また、植え替え後の過程を考慮すると秋植えが一般的です。
植え替えの手順を以下にまとめました。
- 植え替え後の新しい土の準備
- 適切な間隔で植える
- 株を優しく掘り起こし、古い葉や根の除去する
- 植え替え後は水やりと温度・湿度管理を徹底する
それぞれ順番に解説します。
① 植え替え後の新しい土の準備
水はけが良く、有機質が豊富な土を使い、栽培場所が酸性土壌の場合は、苦土石灰を混ぜて1〜2週間前に土壌を整えます。
また、肥料を混ぜて土を作る場合は、元肥として、堆肥や有機肥料を土に混ぜておくと良いです。
② 適切な間隔で植える
実際に、植え替えをする時、植える間隔に注意しましょう。
畑の場合、株間は約25〜30cm、列間は30〜40cmを確保して、プランターの場合、1株ごとに十分なスペースを取ります。
プランターや鉢に植える場合は、きちんと深さが15cm以上ある物を用意するのがおすすめです。
③ 株を優しく掘り起こし、古い葉や根の除去する
現在の植え付け場所から株を優しく掘り起こして、根を傷つけないよう注意しながら取り出し、古い土を軽く落とします。
そして、茶色く枯れた葉や、黒ずんだ根や長すぎる根は剪定ばさみでカットしましょう。
健康な葉と根だけを残すことで、植え替え後の苗への負担が軽減されます。
④ 植え替え後は水やりと温度・湿度管理を徹底する
植え替え後のイチゴの苗は、新しい環境に順応するために温度と湿度の適切な管理が必要です。
また、イチゴの根は細く地に根を張るのに時間がかかるため、しっかり土壌に馴染むように水やりをします。
イチゴは日光を好むため、日当たりの良い場所で育てましょう。
秋植えの場合、寒冷地ではマルチング材や防寒シートを使って霜対策をします。
鉢替えのやり方
イチゴの鉢替えのやり方は、根を傷つけないように植えるのが大切です。
根が曲がらないように広げて植え、株の中心が地面より高くならないように注意します。
植え替え後は乾燥を防ぐために、たっぷり水やりをしつつ、やり過ぎには注意が必要です。
また、病気の伝播を防ぐため、シャベルやハサミは消毒してから使用し、清潔を心がけましょう。