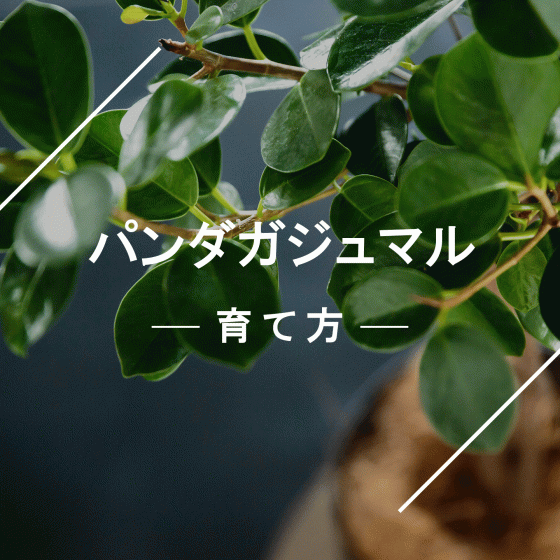ユスラウメの育て方
公開日 2025年10月27日
更新日 2025年10月30日
育てやすさ
初心者の方でも育てやすいのでおすすめです。
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

ユスラウメの基本情報
| 植物名 | ユスラウメ |
| 学名 | Prunus tomentosa Thunb |
| 和名 | 山桜桃梅、毛桜桃 |
| 英名 | downy cherry、Nanking cherry |
| 別名 | 南京チェリー、コリアンチェリー |
| 原産地 | 中国北部、朝鮮半島 |
| 科名 | バラ科 |
| 属名 | サクラ属 |
| 開花時期 | 春 |
ユスラウメは中国や朝鮮半島が原産の落葉低木で、江戸時代に渡来してからは現在も日本全国で広く栽培されています。
花が風にゆらゆらと揺れる様子や、木をゆすって果実を収穫したことに由来して、ユスラウメという名前がつけられました。
日光を好むので地植えで育てるのが一般的ですが、日当たりを確保できれば室内でも育てられます。
春になるとサクラやウメのような花を咲かせ、梅雨に入るころに直径1cmほどのサクランボに似た真っ赤な果実を鈴なりにつけるのが特徴です。
月別栽培カレンダー
種まき
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
植え付け・植え替え
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
肥料
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
開花
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
種類と品種
ユスラウメはバラ科サクラ属に分類される品種で、以下の2つの変種があります。
| 植物名 | 実の色 | 花の色 | 育てやすさ | レア度 |
|---|---|---|---|---|
| ユスラウメ | 赤 | 白、淡いピンク | 初心者向け | ★☆☆☆☆ |
| シロミノユスラウメ | 白、黄 | 白 | 初心者向け | ★★☆☆☆ |
| アカバナユスラウメ | 赤 | 赤、ピンク | 初心者向け | ★★★☆☆ |
いずれの変種も、実と花の色を除いて原種との大きな違いはありません。
シロミノユスラウメ
シロミノユスラウメは、別名「キミノユスラウメ」とも呼ばれる変種です。
白または黄色の実をつけることから、その名前がつけられました。
アカバナユスラウメ
アカバナユスラウメは、赤い実や花をつけるのが特徴的な変種です。
赤い花を咲かせることに由来して名前がつけられました。
ユスラウメとニワウメ(庭梅)の違い
ユスラウメとニワウメは同じバラ科に分類され、花と実の特徴が似ていますが以下のようにいくつかの違いがあります。
| 植物名 | 属 | 葉裏の柔毛 | 樹形 | 樹高 |
|---|---|---|---|---|
| ユスラウメ | サクラ属 | あり | 開帳 | ~3m |
| ニワウメ | ニワウメ属 | なし | 株立ち | ~2m |
ユスラウメ

ユスラウメは、若葉の表と裏に柔毛が生えているのが特徴です。
学名にある「tomentosa」はラテン語で「毛深い」を表していて、柔毛が生えている特徴にちなんでつけられました。
1本の幹から開帳型に枝を広げる樹形をしていて、環境によっては3mくらいにまで大きく成長します。
ニワウメ

ニワウメはユスラウメと異なり、葉っぱに柔毛はありません。
株立ち状(株元から枝が分岐する)に成長する品種で、最大でも2mほどの大きさに留まります。
ユスラウメはどんな花が咲く?

| 色 | 白、淡いピンク |
| 形 | サクラの花 |
| 大きさ | 直径2cm |
| 香り | なし |
| 花びらの数 | 5枚 |
| 開花時期 | 春 |
ユスラウメの花は5枚の花弁で形成されていて、サクラやウメの花に似た形をしているのが特徴です。
華やかな見た目をしていますが、芳香はほとんどありません。
ユスラウメの葉っぱの特徴

| 色 | 緑 |
| 形 | 卵 |
| 大きさ | 3~5cm |
| 触感 | ザラザラ |
| 展開時期 | 4月~ |
ユスラウメの葉っぱは、サクラやウメの葉っぱのように卵形をしているのが特徴です。
表と裏に産毛のようにやわらかい毛が生えていて、両面ともザラザラとした触感をしています。
ユスラウメの花言葉
ユスラウメの花言葉は「郷愁」と「輝き」です。
古くから日本で慣れ親しまれてきた植物で、ユスラウメの果実を食べた幼少期の思い出をイメージしてつけられたといわれています。
ユスラウメの育て方

ユスラウメは乾燥を好む品種なので、土が乾いてから水やりするのが基本の育て方です。
ふくろみ病にかかったりアブラムシがついたりすることがありますが、適切に対処すれば枯れることはほとんどありません。
病気や病害虫を防ぐだけでなく、見栄えを良くするためにも、年に1回のペースで剪定すると良いでしょう。
水やりの頻度
ユスラウメの水やりの頻度は、地植えと鉢植えで異なります。
乾燥に強く過湿に弱いので、頻繁に水を与えないようにしてください。
地植えの水やり
ユスラウメを地植えで育てる場合、植え付け直後は土の表面が乾いたらたっぷりの水を与えましょう。
しっかりと根付いたら雨水で十分なので、基本的に水やりは不要です。
ただし、乾燥状態が長く続く時期には、枝葉が下がったら水を与えてください。
鉢植えの水やり
ユスラウメを鉢植えで育てている場合、土の表面が乾いたら鉢底から流れ出るくらいたっぷりの水を与えましょう。
乾燥しやすい真夏日は、土が乾燥したのを確認したうえで、朝と夕方の2回与えても問題ありません。
冬は控えめに管理しますが、枝葉が下がったら水不足のサインなので、水やりの頻度を増やしてください。
肥料のあげ方
ユスラウメを鉢植えで育てている場合、適切に肥料を与えることで生育が良くなります。
地植えの場合、土に腐葉土もしくは堆肥を混ぜ込んでいれば、基本的に肥料は必要ありません。
施肥する際は、以下のタイミングで緩効性肥料を土にまいて与えましょう。
- 開花後の5~6月
- 落葉期の2~3月
窒素成分が多いと実がつきにくくなる恐れがあるため、リン酸やカリが豊富な化学肥料を使用するのがおすすめです。
落葉期にも肥料を与えることで、生育期を迎えたときに新芽の展開を促す効果に期待できるでしょう。
病害虫・害虫対策
ユスラウメは、ふくろみ病という伝染病にかかったり、アブラムシやカイガラムシが発生するリスクがあります。
放置すると衰弱して枯れてしまう危険性があるため、それぞれの予防法や対処法を理解しておくことが大切です。
ふくろみ(袋実)病
- 実がいびつに肥大する
- 真菌によって感染する
ふくろみ病は真菌による病気で、感染すると果実が袋状に肥大します。
予防するためには、落葉する冬に「石灰硫黄合剤」を散布しましょう。
発症した果実は元に戻ることがなく、放置すると健康な果実にも感染します。
感染して肥大した果実をすべて取り除くことしか有効な対処法はありません。
アブラムシ
- 葉っぱに寄生して栄養を吸い取る
- 非常に高い繁殖力をもつ
アブラムシは葉っぱに寄生して吸汁し、徐々に衰弱させる病害虫です。
日光と風通しを確保できる場所に置いたり、アブラムシ専用の粒状薬剤を土に混ぜたりすることで予防できます。
駆除には、こそぎ落とすか殺虫剤を散布するのが効果的ですが、殺虫剤を使用する場合は果実を収穫した後にしましょう。
カイガラムシ
- 枝や幹から栄養を吸い取る
- 地植えで特に発生しやすい
カイガラムシは、枝や幹から吸汁して弱らせる病害虫です。
室内で育てている場合は日当たりと風通しの良い場所に置くことで発生を防げますが、屋外だと予防するのが難しいとされています。
5〜7月の発生時期にユスラウメの状態をじっくりと観察し、発見したら早急にこそぎ落とすか殺虫剤を散布して駆除しましょう。
剪定
ユスラウメの剪定は11〜3月の落葉期に行うことで、株への負担を最小限に抑えられます。
寒さの厳しい環境で剪定すると枝が枯れてしまう恐れがあるため、寒冷地の場合は比較的温暖な3月ごろに行ってください。
剪定することで以下の効果に期待できます。
- 樹形を美しく整えられる
- 全体の日当たりと風通しを改善できる
- 傷んだ枝を切り取ることで病気を防げる
大きな刈込みには弱いので、必要以上に剪定しないようにしてください。
庭への植え付け方
ユスラウメを地植えする場合、休眠期の2〜3月ごろに植え付けましょう。
植え付け方法は、以下を参考にしてください。
- 日当たりと水はけの良い場所を選ぶ
- 土作りをする
- 植え付けて管理する
① 日当たりと水はけの良い場所を選ぶ
日光を好み過湿に弱い性質があるので、日当たりと水はけの良い場所を選びましょう。
強い日差しが当たる場所でも問題ありません。
② 土作りをする
庭土を掘り起こして、腐葉土または堆肥を混ぜ込みます。
このタイミングで、緩効性肥料をまいてください。
植え付けの3週間前までに土を作っておくことで、土がしっかりと熟成して根張りが良くなります。
③ 植え付けて管理する
根鉢の2倍くらいの深さになるよう穴をあけ、そこに株を植え付けます。
根鉢に土をかぶせたら、たっぷりの水を与えましょう。
しっかりと根付くまでは、土が乾燥したら都度水を与えてください。
盆栽仕立てのやり方
ユスラウメは、鉢に植えて盆栽風に仕立てることも可能です。
盆栽仕立てのやり方は、以下を参考にしてください。
- 鉢を用意して植え付ける
- 水を与えて土を追加する
- 必要に応じて針金かけをする
- 植え替えをして根っこと枝を減らす
① 鉢を用意して植え付ける
鉢を用意し、小粒の赤玉土を入れます。
盆栽仕立てでは、基本的にひとつの鉢に対して植え付ける苗はひとつです。
植え付けたら、周りに赤玉土を足しながら苗を固定してください。
② 水を与えて土を追加する
たっぷりの水を与えて土が下がったら、下がった分だけ土を追加します。
追加したら、再びたっぷりの水を与えましょう。
③ 必要に応じて針金かけをする
ある程度成長したのち、盆栽仕立てで樹形を整えたいなら、枝に針金を巻きつける「針金かけ」が有効です。
枝がもろいため、針金かけをする場合は枝の回復が早い梅雨時期に行うと良いでしょう。
なお、ナチュラルな樹形を楽しみたい方は、無理に針金かけをする必要はありません。
④ 植え替えして根っこと枝を減らす
盆栽仕立てにするなら、鉢のサイズや樹齢にもよりますが1~2年に1回の頻度を目安に植え替えを行います。
コンパクトなサイズ感をキープするなら、このタイミングで伸びすぎた根っこと枝を切り落としましょう。
ただし、強剪定に弱いため、大きく刈り込まないようにしてください。
ユスラウメの栽培環境

ユスラウメは、日光と風通しを確保できる環境で栽培するのに適した品種です。
暑さと寒さの両方に強いので、屋外でも室内でも育てられます。
過湿には弱いので、水はけの良い土で育ててください。
置き場所と日当たり
ユスラウメは日光を好む品種なので、日当たりと風通しが良い屋外で育てるのがおすすめです。
なお、直射日光に長時間当たっても問題なく生育します。
半日陰でも育てることは可能ですが、花や果実を楽しみたいなら、できるだけ日光が当たる場所を確保してください。
適切な温度|どれくらいの寒さまで耐えられる?
ユスラウメの生育適温と耐寒温度は、以下が目安です。
| 生育適温 | 20~30℃ |
| 耐寒温度 | -20℃ |
寒さに強い品種なので、越冬のための対策は特に必要ありません。
氷点下までは常緑ですが、0℃を下回ると落葉します。
なお、落葉する休眠期に水やりを減らし、あえて乾燥を促すことで耐寒性をより高めることが可能です。
ユスラウメの土の配合比率(用土)

ユスラウメは過湿に弱いので、水はけの良い園芸用の土に植えましょう。
鉢植えで土を自作する場合は、赤玉土(小粒)7:腐葉土3の割合がおすすめです。
地植えする場合は、掘り起こした庭土に腐葉土または堆肥を混ぜてください。
ユスラウメの開花時期

ユスラウメは、3~4月の春に花を咲かせます。
開花を促すためには、日光がしっかりと当たる場所で育てることを意識しましょう。
開花時期は3〜4月頃
ユスラウメの開花時期は、3〜4月ごろです。
日当たりを確保すれば、白または淡いピンク色のかわいらしい花をつけてくれます。
ユスラウメの花が咲かない原因は?
ユスラウメの花が咲かない最大の原因は日照不足です。
日光を好む品種なので、開花を促すためには積極的に日光浴させてください。
また,
また、剪定によって花芽を傷つけた場合にも花つきが悪くなるので、剪定する場合は花芽が形成される前の休眠期に行いましょう。
ユスラウメの収穫時期

ユスラウメの果実の収穫は、4〜6月ごろが適期です。
収穫時期になると「赤い宝石」に例えられるほど美しい実になります。
収穫時期は4~6月頃
ユスラウメの果実は、4〜6月ごろに熟して真っ赤になったものを収穫しましょう。
つき始めは緑色をしていますが、熟すにつれて赤く色づきます。
ユスラウメの実がつかない原因は?
ユスラウメの実がつかない場合、以下の原因が考えられるでしょう。
- 生育期にむやみに剪定した
- 日光や肥料が不足している
花芽を傷つけると実がつきにくくなるので、剪定する場合は花芽が形成される前の休眠期に行ってください。
また、日当たりを確保して緩効性肥料を適切に与えるのも、実つきを良くするためには重要です。
収穫のやり方
ユスラウメの果実は、水分を豊富に含んでいてやわらかいので、無理にもぎ取ると潰れてしまいます。
果実を傷つけずに収穫したいなら、以下のやり方を参考にしてください。
- 片手で枝を支える
- もう一方の手で優しく摘み取る
- 摘み取った果実はすぐに容器に移す
ハサミだと果実が傷つく恐れがあるので、直接手で収穫しましょう。
そのままでも食べられますが、酸味が苦手な方はジャムやジュースに加工して食すのがおすすめです。
ユスラウメを種から育てる
ユスラウメは、種からでも比較的簡単に育てられます。
種は基本的に市販されていないので、果実から採種しましょう。
ユスラウメの種まきに適した時期は?
ユスラウメの種まきに適した時期は、3〜4月ごろです。
6〜7月ごろに果実から種を取り出し、翌年の春に播種します。
ユスラウメを種から育てるやり方
ユスラウメを実生する場合、以下の方法を参考にしてください。
- 熟した果実から採種する
- 種まきの適期まで冷蔵庫で保管する
- 育苗ポットに土を入れる
- 土が乾燥しないように管理する
① 熟した果実から採種する
まずは、6〜7月ごろに熟したタイミングで果実を摘み取ります。
果肉を取り除いたら、種をしっかりと水洗いしてください。
② 種まきの適期まで冷蔵庫で保管する
種が乾燥しないよう、湿らせた水苔や川砂と一緒に密閉できる保存袋に入れましょう。
種が乾燥すると発芽率が著しく下がるため、種まき適期の翌春まで冷蔵庫で保管してください。
種まきするときは、あらかじめ冷蔵庫から取り出し常温に戻しておきましょう。
③ 育苗ポットに種をまく
3号の育苗ポットを用意し、市販の種まき用の土または小粒の赤玉土を入れます。
ひとつの育苗ポットにつき、1粒の種をまいてください。
④ 土が乾燥しないように管理する
土が乾燥しないよう、こまめに水やりして管理します。
株の大きさが15〜30cmほどになったら、新しい鉢または庭土に定植してください。
ユスラウメの増やし方

ユスラウメをすでに育てている場合、健康な枝をカットして挿し木で増やすことが可能です。
ここからは挿し木に加え、植え替えに適した時期や手順についても解説していきます。
挿し木の時期はいつがいい?
ユスラウメを挿し木で増やすなら、生育が旺盛な7月に行うのがおすすめです。
健康な新枝を選ぶことが、発根率を高めるために重要となります。
挿し木のやり方
ユスラウメの挿し木は、以下の手順で行なってください。
- 健康な枝をカットする
- 挿し木を水に浸す
- 挿し木を植え付ける
- 管理して定植する
① 健康な枝をカットする
まずは、健康な新枝を選び、15cmほどの長さになるようカットしましょう。
切り口を斜めにすることで、吸水面積が増えて発根しやすくなります。
葉っぱは2枚ほど残し、切り口付近の葉っぱは摘み取ってください。
② 挿し木を水に浸す
容器に水を入れ、挿し木の切り口を2〜3時間ほど水に浸します。
水揚げしたら、切り口にメネデールやルートンなどの発根促進剤をなじませてください。
③ 挿し木を植え付ける
鉢に市販の挿し木用土もしくは小粒の赤玉土を入れ、挿し木を植え付けます。
複数本植え付ける場合は、鉢の縁に沿わせて密集させないようにしましょう。
④ 管理して定植する
植え付け後は、乾燥しないようこまめに水を与えてください。
湿度をキープしながら明るい日陰で管理すると、1ヶ月ほどで根っこが出てきます。
発根したら、新しい鉢または庭土に定植してください。
植え替え時期はいつがいい?
ユスラウメを鉢植えで育てている場合、2〜3月ごろに植え替えましょう。
成長するにつれて根っこが詰まってくるので、最低でも2〜3年に1回の頻度で一回り大きな鉢に植え替えてください。
鉢替えのやり方
ユスラウメの鉢替えは、以下の手順で行いましょう。
- 鉢から株を抜く
- 新しい鉢を用意する
- 植え付けて管理する
① 鉢から株を抜く
まずは、鉢から株を抜いてください。
鉢替え前に土を乾燥させ、土ごと抜き取ると根っこを傷めずにすみます。
根鉢を優しくほぐしながら、古い土を落としましょう。
② 新しい鉢を用意する
新しい鉢は、根鉢より一回り大きいサイズのものを使用します。
鉢を用意したら、水はけの良い土を入れましょう。
③ 植え付けて管理する
株を新しい鉢に植え付けたら、下から漏れ出すくらいたっぷりの水を与えてください。