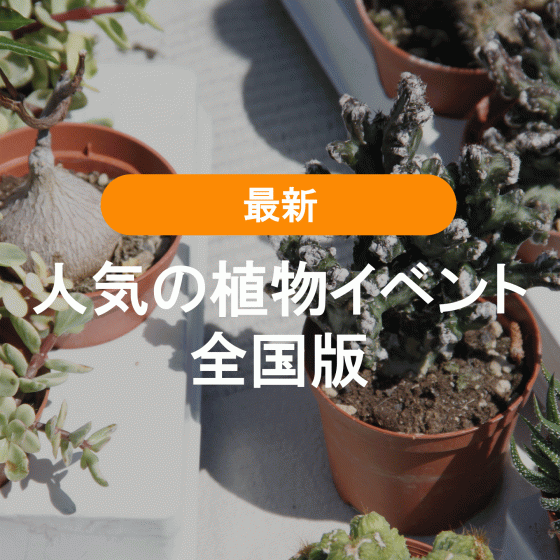観葉植物にきのこが生える原因と対処法
公開日 2025年04月21日
更新日 2025年04月23日
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX
目次
観葉植物にきのこが生える一番の原因は高温多湿
家庭で育てている観葉植物にきのこが生えてくる一番の原因は高温多湿です。
森や林の中の湿気がたまりやすい窪地や朽ち木に生えているのをみれば分かるとおり、きのこはジメジメとした暗い環境を好みます。
きのこが生えるのは高温多湿で繁殖しやすい状況が整っているという証拠です。
観葉植物の生育にとってあまり良い状態ではないので、現在の室内環境や用土を見直しましょう。
なお、きのこが生えるには種となる胞子が必要で、主に以下の2つの経路で混入します。
| 風で飛んでくる | 胞子は花粉よりも小さいため、風に乗って庭やベランダに飛んできて室内にもいつのまにか入ってくる |
| 土の中に混ざっていた | 腐葉土や市販の培養土などに元から混入していた |
腐葉土やバーク堆肥、市販の培養土などは殺菌されていないものがほとんどで胞子が混入している可能性が高いです。
また、こういった有機質の土はきのこの栄養にもなるので、生やしたくなければ使用するのは避けましょう。
観葉植物に生えるきのこの種類
観葉植物に生えるきのこは環境や条件によって様々です。
以下で、観葉植物に生えるきのこを一部紹介します。
食用とされているものもありますが類似した有毒種も多数あり、きのこの種類を見た目だけで同定するのは難しいため、あくまで参考程度にして口にしないようにしてください。
また、野生のきのこは食用でも微量の毒を含む種類があるので食べないのが無難です。
観葉植物に生える白いきのこはキコガサタケ

キコガサタケは白っぽいクリーム色をしていて三角帽のようなかさをつけるのが特徴です。
観葉植物以外では主に芝生に発生します。
全体的に華奢で肉が薄く、日に当たるとすぐに萎むため朝に生えていても夕方には無くなってしまうことも多いです。
軸径は0.1~0.3cmと極細ですが、長さは5~8cmほどあります。
成長するとかさの縁部分がやや反り返るのもポイントです。
観葉植物に生える黄色いきのこはコガネキヌカラカサタケ

黄色いきのこが生えた場合はコガネキヌカラカサタケの可能性があります。
コガネキヌカラカサタケは全体的に黄色のきのこで、小さなつぶつぶがついた丸いかさをもつのが特徴です。
寿命が短く1~3日で萎むため見かける機会が少ないことや、生えたばかりの姿が黄金色のお釈迦様に似ていることから「幸福のきのこ」「お釈迦様のきのこ」と呼ばれています。
観葉植物に生える茶色・灰色っぽいきのこはヒトヨタケ

茶色や灰色でシルクのような光沢があるきのこです。
かさが開くと黒いインクのような液を垂らして「一夜で溶けてしまう」ことが名前の由来となっています。
かさの中央に褐色の鱗片と呼ばれる褐色の突起があり、かさ径は5~8cm、軸の長さは8~15cmとやや大きめです。
観葉植物に生えるきのこが及ぼす影響はある?
きのこが観葉植物に直接悪影響を及ぼすことはありません。
きのこは土中の有機物を分解して栄養のある土にしたり、植物の根に共生してお互いに栄養を与えあったりして生きています。
そのため、きのこが生えたせいで観葉植物が枯れることはありません。
ただ、きのこが間接的な影響を及ぼすことはあります。
きのこが及ぼす間接的な影響
- コバエの温床になる
- 胞子で部屋が汚れる
- 大量発生時は水はけが悪くなる
観葉植物にきのこが生えるとコバエが寄ってきやすくなります。
特にきのこを好むキノコバエが発生しやすいので注意が必要です。
また、きのこは菌糸と呼ばれる白い糸状の細胞を土中に張り巡らせるため、大量に発生した場合は水はけが悪くなるといった影響があります。
観葉植物にとっては直接的な悪影響を及ぼすことはありませんが、きのこには毒があるものもあるので小さな子どもが口にしないように注意しましょう。
きのこが生えるメリットもある
観葉植物にきのこが生えることはデメリットだけではありません。
きのこは土中の有機物を分解して植物が吸収できる形にしたり、植物の根を介してチッ素やリン、カリウムなどの養分を供給したりするというメリットもあります。
つまりきのこは、植物の養分吸収を補助し生育の促進に役立っているということです。
また、土中を植物に有益な菌で満たし、害のある菌の侵入や繁殖を抑制する作用もあります。
スピリチュアルでは幸運を意味する
スピリチュアルでは観葉植物に生えるきのこは幸運が訪れる前触れとされています。
きのこが生えてきたのは、植物が健康でエネルギーに満ちていて滞りなく循環しているためと考えられ、これは自然界からの祝福のサインであると捉えられているからです。
なかでも金色や鮮やかな色合いを持つ種類は「幸運のきのこ」と呼ばれています。
特にコガネキヌカラカサタケは、その金色の輝く姿から金運や繁栄を象徴とされ、出会うことがあれば「幸運」や「願いが叶う」といわれています。
対処法|観葉植物にきのこが生えたら手袋で取り除く

観葉植物に生えたきのこを取り除く場合はゴム手袋などをして作業しましょう。
きのこは根を張っているわけではないので簡単に引き抜けます。
きのこを除去する際のポイント
- 除去したきのこを捨てる時は密封する
- 使用した手袋は流水でしっかり洗う
- 使い捨てのビニール手袋を使用するのもおすすめ
- 除去後は鉢を日当たりのいい場所に置き菌を死滅させる
きのこの除去は胞子が飛ばないようにするのが重要です。
捨てる時は袋で密封し、胞子がついた手袋はしっかり流水で洗いましょう。
日光を当てても土の中にいる菌まで死滅させるのは難しいので、完全に除去したい場合は植え替えをするのが効果的です。
また、再度きのこを発生させないように水やりの頻度や環境を見直しましょう。
観葉植物にきのこを生やさないための予防法
観葉植物にきのこを生やさないためには、胞子の混入がない土への植え替えや有機質肥料を化成肥料に換えるといった方法で予防できます。
胞子と有機物をセットにしないようにするのがポイントです。
また、風通しの良い場所に置いて蒸れないようにするのも根本的な対策になります。
以下の解説を参考にして観葉植物にきのこが生えるのを予防しましょう。
新しい土に植え替える(無機質な土や殺菌した土)
観葉植物にきのこを生やさないためには無機質な土や殺菌した土への植え替えが効果的です。
また、きのこは有機物の表面にしか生えないため、赤玉土や鹿沼土、バーミキュライトやパーライトなどの無機質な土を使用すると生えにくくなります。
植物にあわせた比率で配合して使用しましょう。
無機質な土は栄養分を含まないため、肥料が必要な場合は元肥として化成肥料を入れます。
自宅でできる土の殺菌方法
殺菌した土は市販品のほか、今ある土を日光で殺菌して使用することも可能です。
土の殺菌は以下の手順で行います。
- 土中に残った根などを取り除く
- ビニール袋に土を入れる
- 土に水を含ませる
- 袋を閉じて日が当たる場所に置く
- ひっくり返してまんべんなく光を当てる
- 20日ほど置いたら完了
① 土中に残った根などを取り除く
鉢から株を抜き、土中に残った根や枯葉などを取り除きます。
② ビニール袋に土を入れる
黒いビニール袋よりも透明の方が温度が上がるのでおすすめです。
できるだけ土は薄く広げて入れます。
③ 土に水を含ませる
じょうろなどを使って土がある程度湿るくらい水を含ませます。
④ 袋を閉じて日が当たる場所に置く
袋の口を閉じて、直射日光が当たるコンクリートの上などに置きます。
置いておく期間は20日ほどが目安です。
⑤ ひっくり返してまんべんなく光を当てる
5日に1回くらい袋をひっくり返してまんべんなく光を当てます。
土の量が多くて厚ければ中のほうもかき混ぜます。
⑥ 20日ほど置いたら完了
20日ほど日光に当てたら殺菌完了です。
太陽熱を利用して殺菌するため、7月中旬から9月上旬が適した時期になります。
また、殺菌した土は菌が死滅した状態ですが、土の構造が壊れて栄養も無い状態です。
そのままでは水はけが悪いため、使用する際は赤玉土や鹿沼土を入れて排水性を上げ、必要であれば化成肥料も施して使用しましょう。
有機肥料を化成肥料に変える
きのこが生えるのを予防するには、有機肥料を化成肥料に変えるのもおすすめです。
きのこは有機物を分解して栄養として取りこむので、油かすなどの有機肥料を使用しているときのこが生える場合もあります。
きのこを生やしたくない場合は有機肥料をやめて、化成肥料を使用しましょう。
さらにきのこの発生確率を下げたい場合は無機質の土に変えると効果的です。
風通しを良くして多湿を防ぐ
きのこは多湿な環境を好むため風通しを良くするのが大事です。
置き場所はできるだけ日当たりと風通しを良くして、蒸れたり湿気がたまったりしないようにするときのこが生えるのを予防できます。
特に夏場の締め切った部屋は高温多湿になるので、水やりをしたあと置いておくと一晩できのこが発生する場合もあるので注意が必要です。
風通しが良い場所が確保できない場合はサーキュレーターなどで風を送ってあげるときのこの繁殖もしにくく、病気の予防にもなります。
また、水のあげすぎも多湿の原因になるので水やりは適切な頻度を守りましょう。
殺菌剤や木酢液を使う
殺菌剤や木酢液を使用するときのこが生えるのを予防できます。
木酢液とは、炭を焼いたときの煙を冷却してできた液体で、植物の成長促進や虫除け、殺菌作用があるものです。
殺菌剤や木酢液は白絹病やスス病、うどんこ病といったきのこと同じ真菌による病気にも効くので、きのこの発生を予防する効果も期待できます。
土の中や表面に散布すると菌を死滅できるので、何度もきのこが生えてくる場合におすすめです。
観葉植物にきのこは珍しくない!慌てずに対処しよう
ここまで紹介してきたように観葉植物にきのこが生えるのは珍しくありません。
生えたきのこは引き抜いて、殺菌剤を散布したり、土を無機質のものに換えたりして対応しましょう。
また、きのこが生えるのは悪い事ばかりではなく、植物と共生し栄養を供給するといった良い面もあります。
HanaPrimeで購入した観葉植物を育てる際にもきのこが生える場合がありますが、どちらかといえばきのこが生えるような高温多湿でジメジメした環境が問題です。
置き場所や日当たり、水やりの頻度や土の排水性などを適切に管理して、観葉植物を元気に育てましょう。