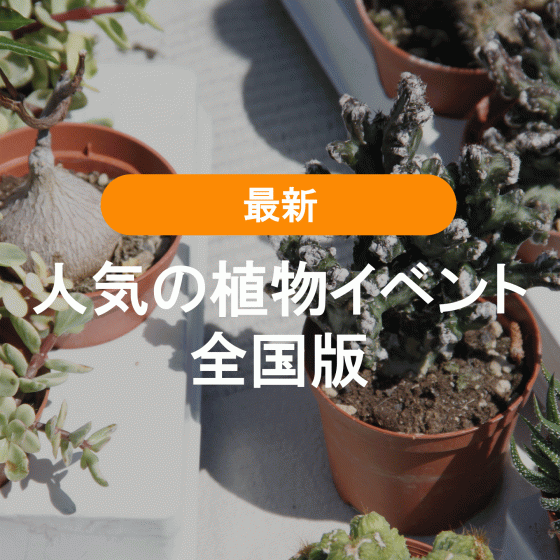観葉植物に赤玉土を使うメリットとデメリット
公開日 2025年01月08日
更新日 2025年12月19日
監修者情報

覚張大季
植物と人との関わりに魅了され、日本各地の植物農園を見て回る。HanaPrimeの植物部門の立ち上げ後はオフィスや商業施設、個人宅など、幅広いシーンのグリーンコーディネートを数多く担当。植物の生態や特性を深く掘り下げ、それぞれの空間やライフスタイルに適したグリーン空間デザインを提案することが得意。観葉植物の世界に情熱を注ぎ、植物の価値を最大化することを使命としている。

INDEX
目次
観葉植物に使える「赤玉土」とは

観葉植物の育成に使える「土」には、いくつか種類があります。
そのなかのひとつ「赤玉土」は、関東の土壌から採取される赤土で作られた園芸用土です。
関東平野に広がる火山灰層「関東ローム層」を元に、粒径をそろえたものが流通しています。
粒のサイズが小さい順に細粒・微塵・極小粒・小粒・中粒・大粒と分類されているので、使う際には育てる植物に合うタイプを選びましょう。
観葉植物に赤玉土を使うメリット
赤玉土を使って観葉植物を育てると、コバエの発生が最小限に抑えられ、植物の生育が促進されるなど、さまざまなメリットがあります。
コバエが発生しにくい
観葉植物を育てていると「コバエ」が発生する場合があります。
コバエは、土に含まれる有機物を好むため、一般的に有機物を多く含む観葉植物用の土は、コバエにとっては絶好の住処です。
しかし、赤玉土は有機物を含んでいないので、コバエの発生を防げます。
一度コバエが発生すると退治に手間も時間も掛かるので、なるべく楽に害虫対策をしたいと考える方には非常におすすめです。
通気性・排水性が高いので生育がよい
赤玉土は等しい大きさの粒が集まってできた土なので、粒と粒の間には必ず隙間ができます。
粒の間に空気や水が通りやすいので観葉植物の生育を促すにはぴったりな土です。
専用に販売されている赤玉土はもちろん、市販の培養土の一部として混ぜても観葉植物用の土として使えます。
通気性・排水性を求める場合には粒子が大きなもの、水持ちを良くしたい場合には粒子の小さいものを選んでください。
保水力・保肥力が高い
排水性の良い赤玉土ですが、土自体は粘土質なので粒の一粒ずつは保水力や保肥力にも優れています。
実際には排水力よりも保水力のほうが上回るものの、ほかの土と比較すると充分に排水力に優れているため、根腐れなどの心配はいりません。
また、一度肥料を与えると土がしっかりと肥料分を保ち続けてくれます。
肥料に掛かる費用を抑えられ、さらには植物に必要な栄養を植物全体に効率よく届けられるのが魅力です。
弱酸性の用土なので幅広い観葉植物に適している
赤玉土はpHが5〜6前後で、多くの植物が好むとされている「弱酸性」の用土のひとつです。
幅広い観葉植物に適していて、ほかの土や肥料との組み合わせ次第ではどんな植物にも使える土と言えます。
どのような基本用土を選べば良いか迷った際には、まず赤玉土を候補に入れて、育てる植物に適しているかどうかをチェックしてみてください。
観葉植物に赤玉土を使うデメリット
メリットが多い赤玉土ですが、いくつかデメリットと言える点もあります。
赤玉土を使用する際には、デメリットも理解したうえで、自分なりに工夫や注意しましょう。
保水力が高いので根腐れが起きやすい
乾燥を好む植物の場合、赤玉土は適していません。
ほかの土と比較して排水性に優れている点がメリットですが、同時に保水力も高いため土の乾きが遅くなってしまう傾向にあります。
とくに、過度な水やりは根腐れを起こす恐れがあるので注意しましょう。
赤玉土は幅広い植物に適している土のひとつですが、なかでも潤いを求める植物にこそぴったりな土です。
重いので大型の鉢に使用する場合、移動が大変
赤玉土は比重が約0.8と、園芸用に使われる土のなかでは重さのある土です。
一般的な土の比重は0.4〜0.5程度とされているため、重さで移動が大変かもしれません。
大型の鉢で多くの土を使うなら、腐葉土や植物性堆肥といった有機物を混ぜてみてください。
重さのみならず品質面でもバランスの良い土になるのでおすすめです。
時間が経つと粒が崩れて通気性・排水性が悪くなる
等しい大きさの粒が集まっている赤玉土は、空気や水が通りやすい点がメリットです。
しかし、観葉植物の用土として使用して長く時間が経つと、少しずつ粒の形が崩れてきてしまいます。
粒が崩れるにつれ通気性や排水性も少しずつ悪くなっていくので注意してください。
メリットを最大限に生かしたいと考える場合には、目詰まり解消のためにたっぷりと水を与えたり土を入れ替えたりしてみるのがおすすめです。
リン酸を吸収して生育に悪影響を及ぼすことも
植物の成長にはチッ素、リン酸、カリウムの三大要素が重要なため、観葉植物も肥料を使って必要な栄養を補うと元気に育ちます。
赤玉土は三大要素のひとつである「リン酸」と少し相性が悪く、リン酸不足を招く可能性があるのを覚えておきましょう。
リン酸が不足すると植物の幹が太くならなかったり、花ぐされが出やすくなったりとさまざまな弊害が起きてしまうため、対策が欠かせません。
リン酸不足の回避には、植物性堆肥や家畜糞の堆肥、または粘土鉱物などを土に混ぜるのがおすすめです。
粒のサイズによって異なる赤玉土の使い方
大小さまざまな粒の種類がある赤玉土は、それぞれ異なった使い道があります。
大粒・中粒・小粒・細粒についてそれぞれの特徴と用途があるので、購入の際には参考にしながら選んでみてください。
| 粒の種類 | 粒の大きさ | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 大粒 | 直径約1cm | 排水性に優れている | 鉢底石にする |
| 中粒 | 直径約7mm~1cm | 水はけと保水力のバランスが良い | オールマイティに使える |
| 小粒 | 直径約5~7mm | ほどよく水がはける | 大粒や中粒に混ぜる |
| 細粒 | 直径2mm以下 | 粒の隙間がほとんど無い | 挿し木用として |
大粒は「鉢底石」に使う

直径1cmほどの最も大きな粒だけを集めたものは、用土として単体では粒が大きすぎるため排水性がありすぎて向いていません。
しかし、他の土に混ぜたり「鉢底石」として利用したりと、用途はたくさんあります。
とくに、鉢底石は水はけの向上が目的なので、粒と粒の隙間が大きな大粒タイプがぴったりです。
中粒は「鉢底石」「鉢植えの土」に使う

中粒は、粒の種類のなかでは最も幅広い使い方ができるサイズです。
鉢植えに使うメインの土としてはもちろん、鉢自体のサイズが小さい場合には大粒タイプのように「鉢底石」としても利用できます。
水はけに優れている一方で保水力とのバランスも良いので、初めて選ぶ際にはまず中粒を選ぶと間違いありません。
小粒は「鉢植えの土」に使う

小さくて細かい粒を集めた小粒タイプの赤玉土は、主に鉢で観葉植物を育てる際に使用します。
小型の鉢に向いていて、ほどよく水がはけたり留まったりする扱いやすい土です。
鉢や育てる植物のサイズに合わせて、大粒や中粒と組み合わせながら使います。
細粒は「挿し木」などに使う
細粒は、直径が2mm以下の細かな粒を指し、3号以下の鉢やテラリウムの用土として活躍します。
粒の隙間がほとんど無くて水はけが悪いので、乾燥を好む植物に細粒は適していません。
基本的には「挿し木」用ですが、小粒と混ぜれば栽培用土としても利用可能です。
室内の観葉植物用に赤玉土で培養土を作る方法
植物は室内用と屋外用で向いてる土の特徴が異なるので注意が必要です。
今回は、主に室内での育成がメインとなる「観葉植物用」の土について紹介します。
赤玉土をメインとして培養土を作るのであれば、ほかに混ぜるのは軽石の一種である鹿沼土、腐葉土、または鉱物を加熱してつくられたバーミキュライトなどです。
材料は、鉢(容器)に足りるだけの量を用意し、育てる植物の特性に合わせて配合を決めましょう。
たとえば、赤玉土、鹿沼土、バーミキュライトの配合例は以下の通りです。
| 用途 | 赤玉土 | 鹿沼土 | バーミキュライト |
|---|---|---|---|
| 汎用性の高い基本配合 | 60% | 30% | 10% |
| 水はけを良くする配合 | 50% | 25% | 25% |
| 一般的な観葉植物向け | 40% | 40% | 20% |
今回であれば赤土玉のように、メインの土の割合を一番多く設定してから残りの割合を決めるのがおすすめです。
コバエの発生を抑えたい場合にはバーミキュライトを使用し、匂いが気になる場合には堆肥の使用は避けましょう。