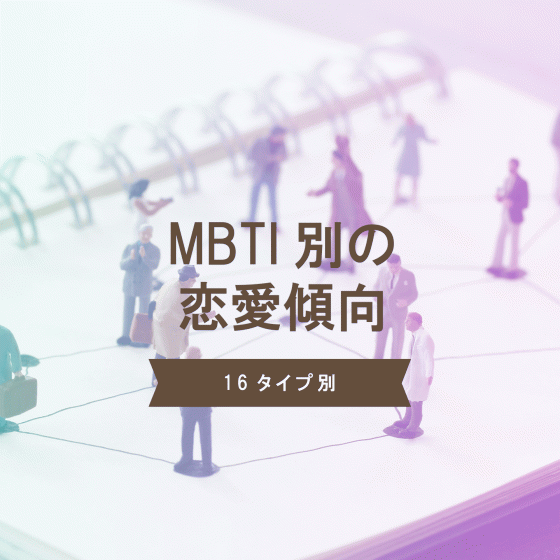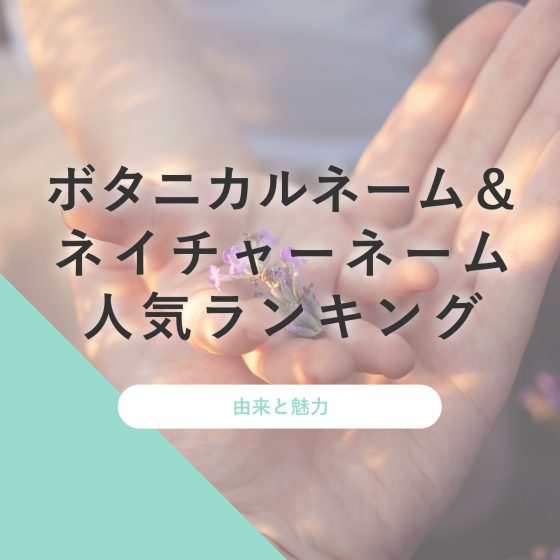端午の節句とこどもの日の違いを詳しく解説
公開日 2024年02月21日
更新日 2025年06月19日
毎年5月5日は「こども日」の名前で知られる国民の祝日です。
また、同じく5月5日を「端午の節句(たんごのせっく)」と呼ぶこともあります。
日付が同じであることから、両者は同一視されることがありますが、本来は別の行事です。
そこで、こどもの日と端午の節句の違いに加えて、それぞれの起源や由来、風習、お祝いの仕方などについて詳しく紹介します。

目次
INDEX
こどもの日と端午の節句の違い|歴史と由来
| こどもの日 | 男女問わず子どもの成長を祝う国民の祝日 |
| 端午の節句 | 男の子の健やかな成長を願う行事 |
5月5日は「こどもの日」として知られていますが、同時に「端午の節句」ともいわれます。
多くの人が混同しがちですが、本来はそれぞれ異なる意味があります。
こどもの日|男女問わず子どもの成長を祝う国民の祝日
こどもの日は日本国民の祝日の1つで、5月3日の「憲法記念日」、4日の「みどりの日」に続く、3連休の最終日、いわゆるゴールデンウイーク期間に含まれます。
国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条によると、こどもの日は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを目的に、1948年に制定されました。
端午の節句(たんごのせっく)|男の子の健やかな成長を願う行事
古代中国の陰陽五行節によると、季節の変わり目である5月は体調を崩して亡くなる方が多く、特に5日は同じ奇数が重なって、縁起の悪い日と考えられていました。
そこで、5月5日に厄払いを行ったのが、端午の節句の起源といわれています。
日本では、奈良時代から端午の節句を祝う行事がはじまったとされており、男の子が生まれてから最初に迎える端午の節句を「初節句(はつぜっく)」といいます。
端午の節句は五節句の名残り
「節句(せっく)」とは古代中国の陰陽五行説に由来する暦のことで、季節の節目にあたることから、伝統的な年中行事を行うのが一般的でした。
五節句には、1月7日の「七草の節句」や7月7日の「七夕」などがあります。
明治時代になってから五節句は廃止され、5月5日の端午の節句のみ、こどもの日の名称で祝日に制定され、現在も休日として残っているのです。
こどもの日と端午の節句の違い=祝日と行事
結論として、こどもの日は「国民の祝日」、端午の節句は「行事」ということができます。
現在では、こどもの日も端午の節句も同義語として認識されており、祝日でもあることから「子どもの成長をお祝いする日」として定着しています。
こどもの日の祝い方と意味合い

こどもの日の休日には、子どもを主役とした祝い方がいくつかあります。
昔ながらの伝統的なお祝いの代表格は、「鯉のぼりを飾る」こと。
他にも様々なお祝いの方法があり、それぞれの事柄には子どもの成長を願う意味が込められています。
① 鯉のぼりを飾る
「屋根より高いこいのぼり」という童謡でも親しまれている鯉のぼり。
鯉が激流に逆らってたくましく川を登っていく姿から、たくましく育って欲しいという願いから来ています。
こいのぼりを庭先などに飾る習慣が定着したのは、江戸時代になってからのことで、マンションなどが多い今日では、ベランダに飾る人も多いです。
② 兜や五月人形を飾る
こどもの日に兜や鎧を飾るのは、鎌倉時代の武家社会で誕生したならわしといわれています。
当時、兜や鎧などの武器は自分の身を守るための大切な道具であり、安全祈願のために神社に奉納するしきたりがありました。
そのため、無病息災を祈る意味を込めて、身を守るアイテムである兜や鎧を飾る習慣が今も残っているのです。
③ 菖蒲湯に入る
菖蒲湯は、菖蒲の葉や根を入れて沸かしたお風呂のことです。
薬用として使われる菖蒲には、血行促進、痛みの緩和、保湿、リラックス作用などがあり、健康への良い効果が期待できます。
菖蒲湯の由来は、厄除けに飾られる菖蒲の葉が、剣をイメージさせることや、読み方が「尚武(しょうぶ)」と同じであることであるといわれています。
※「尚武」とは、武道や軍事などを重んじることです。
④ 家族でレジャーに出かける
こどもの日は子どもが主役なので、家族でレジャーに出かける家庭も多いです。
子どもがのびのびと全身を使って遊べる大きな公園やアスレチック、遊園地、動物園や水族館など、子どもと大人が一緒になって楽しめる場所に遊びに出かけるのが一般的です。
家族で体を使って1日中アクティブに遊べば、普段できない体験もでき、こどもの日の思い出として後々まで記憶にも残りますね。
⑤ 自宅に季節のお花を飾る

胡蝶蘭 大輪 36輪~39輪 3本立ち 白
白の3本立ちで、1本あたり12~13輪もの花が咲いている姿はとても豪華で素敵です。とてもリーズナブルな価格で提供しております。花言葉「幸福が飛んでくる」が意味するように、お祝いからお悔やみまで幅広くご利用いただけます。
詳しく見る
自宅に季節のお花を飾って祝うのもおすすめです。
特に、五月人形の横にスペースがあれば花瓶に菖蒲の花を活けたりするご家庭も多いでしょう。
5月が旬のお花は以下のようなものがあります。
他にも、お祝いごとに欠かせない胡蝶蘭もおすすめです。
お祝いごとの定番「胡蝶蘭」は、年中通して流通しており、おじいちゃんおばあちゃんや親戚からの贈り物として人気があります。
こどもの日にふさわしい食べ物

子どもの日をお祝いするには、柏餅などの縁起物の食べ物も欠かせません。
ちなみに、かしわもちは主に関東、ちまきは関西や中国でよく食べられています。
関西地方でちまきがよく食べられるのは、柏の木は関東以北に多く生息し、関西圏では生育が難しい植物だったのが理由の1つと考えられています。
① 柏餅
かしわもちは、上新粉でつくった丸い平形のもちに、あんをはさみ、柏(かしわ)の葉で包んだ和菓子です。
柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、「家系が途絶えない」「子孫繁栄」の縁起物として、端午の節句に欠かせない節句料理の1つです。
ちなみに、かしわもちを食べるのは日本独自の習慣で、中国では見られません。
② ちまき
ちまきは、蒸したもち米を三角形にし、笹や茅(ちがや)でくるんでイグサなどで縛った食べ物です。
中国の端午の節句の風習とともに日本に伝わったもので、甘い味ではありませんが、一般的に「菓子」に分類されています。
ちまきには邪気払いや無料息災といった意味があります。
③ お子様ランチ
柏餅やちまきは主にお菓子ですが、こどもの日のごはんはお子様ランチにするという家庭も多いです。
お子様ランチは子どもの好きなメニューが詰まっているので子どもの喜び、いろいろな具材が少しずつ入っているので栄養的にもバランスが取れるのでおすすめです。
④ デザート(ゼリー、ケーキ)
こどもの日は、1年でお誕生日以外に子どもが主役になる特別な日。
ごはんのあとには、子どもが喜ぶデザートも用意しましょう。
ゼリーやケーキなど、子どもと一緒に作ったりデコレートしたりすると、より楽しく思い出に残るでしょう。
こどもの日・端午の節句に関するよくある質問
ここまで読み進めた人の中には、上記以外の疑問を持つ人もいるでしょう。
最後に、こどもの日や端午の節句に関する、よくある質問について解説します。
端午の節句は女の子もお祝いしていい?
端午の節句は男の子の行事なので、基本的には男の子のお祝いです。
ただし、子どもの日は男女関係なく「子どもの成長を祝う」ので、こどもの日として祝うのであれば問題ありません。
ちなみに、女の子のお節句は、3月3日の上巳「桃の節句」です。
この日はお雛様を飾り、女の子の成長をお祝いする行事として、今でも全国各地で伝統的に祝われています。
こいのぼりはいつからいつまで飾る?
こいのぼりを飾り始める日に特に決まりはありませんが、一般的には3月下旬か4月上旬が多いようです。
しまうタイミングはできるだけ早いほうが良く、こどもの日の翌日から1週間以内には片します。
長く外に出しておくとホコリや雨にさらされて汚れてしまったり、太陽の光で色褪せてしまう可能性があるからです。
五月人形は誰が買う?
昔は母方の祖父母が買うのが一般的でした。
しかし、今は両家の祖父母で相談して購入したり、親が直接買うことも多くなりました。
五月人形は高価なものですので、各家庭の事情によって決めるのがおすすめです。
柏餅とちまきはどっちを用意する?
柏餅とちまき、どちらを用意するかは、地域によって異なります。
一般的には柏餅は関東圏、ちまきは関西圏が多いですが、特に決まりはないため、食べたい方を用意すると良いでしょう。
もちろん、両方用意しても問題ありません。