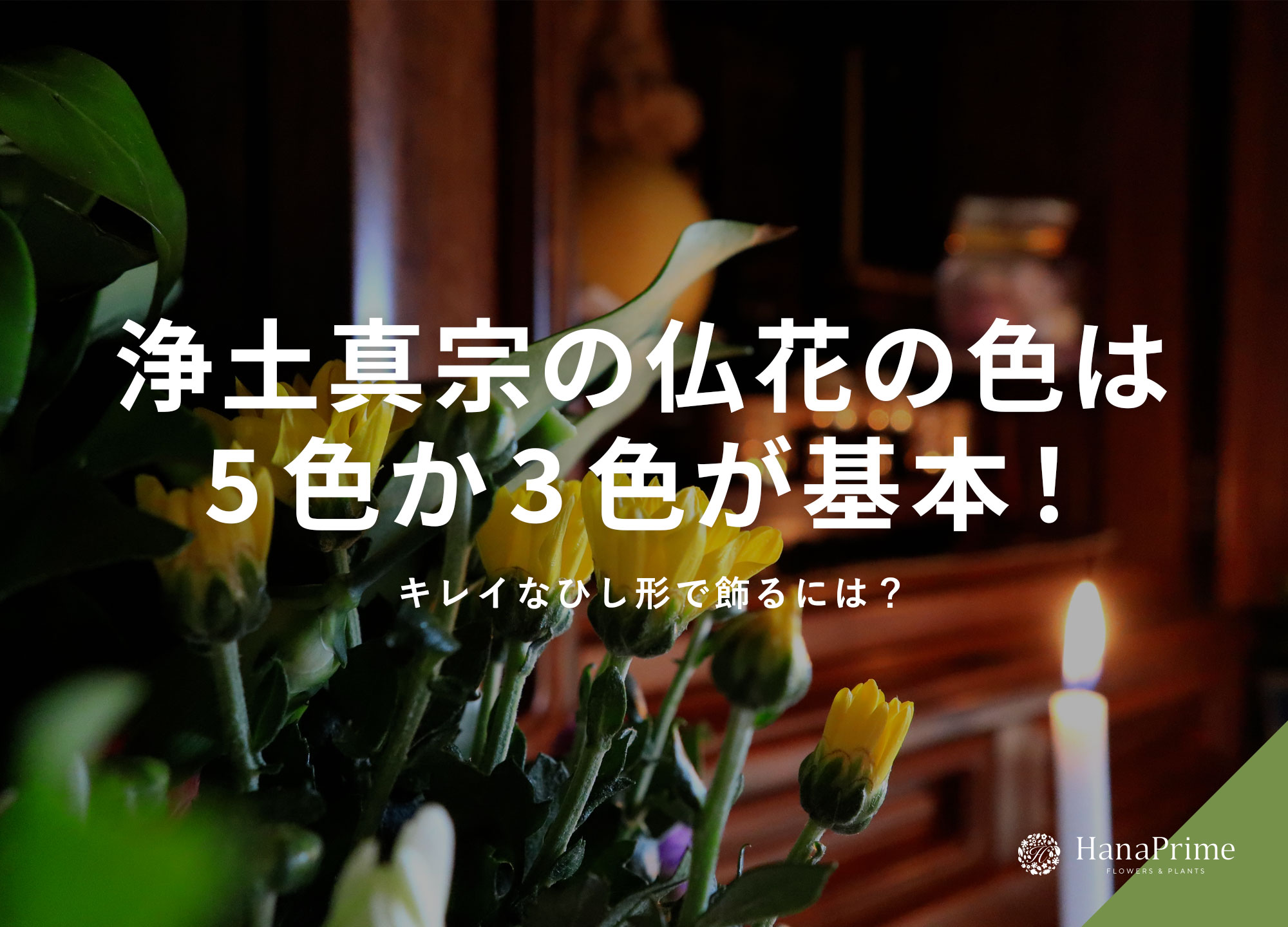
"浄土真宗の家庭であれば、仏花を仏壇に飾る際に、本当にこれで合っているのか?と迷うこともありますね。
他にも「浄土真宗のお仏壇にどんな花を飾る?」「ふさわしくないお花の種類や飾り方もある?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。
本記事では、浄土真宗のお仏壇に生けるお花の選び方や、避けるべき花の特徴、さらには仏壇への飾り方のマナーについて詳しく解説します。
浄土真宗における仏花の選び方、生け方、飾り方のコツをまとめてご紹介。お仏壇を持つ家庭の方はぜひ参考にしてみてください。
HanaPrimeでは、浄土真宗の仏花としてぴったりなお花を数多く取りそろえています。
\16時までのご注文で当日発送/
目次
浄土真宗における仏壇のお供えの基本
仏教は、宗派によって仏壇のお供え物が異なります。
特に浄土真宗は、ほかの宗派と異なる部分がいくつかあるので、これから準備する場合には以下の内容を必ず確認しておきましょう
仏壇の5つのお供え物「五供(ごく)」とは
仏壇に供える5つのお供え物を「五供(ごく)」といいます。
以下は、浄土真宗以外で用いられる一般的な五供の一覧です。
一般的な仏教で使われる五供一覧
| お供え物 | 意味 |
| 香:お線香 | 場所や参拝者の心身を清める |
| 灯明:ロウソク | 闇を払う仏様からの導き |
| 花:生花 | 香りや見た目で安らぎを与える 生命の尊さと仏の慈悲を表す |
| 飲食(おんじき):ご飯 | 不自由なくご飯が食べられることへの感謝 仏様は湯気を食すとされる |
| 浄水:水・お茶(浄土真宗では不要) | 仏様の喉が渇かないように供える 参拝者の心身を清める |
上記のうち、浄土真宗では浄水をお供えしません。
浄水の代わりに、樒(しきみ)と呼ばれる植物をお供えする決まりとなっています。
仏壇の花は一対でないとダメ?
仏壇の花は、一対でなくても問題ありません。
基本的に、三具足であれば1つだけ(一基)、四具足や五具足の場合は一対となるように飾ります。
最近では、コンパクトなモダン仏壇を使用する場合も多く、一基で飾るケースも少なくありません。
一基だと仏様や故人に失礼といったこともないので、ご安心ください。
水やお茶はお供えせず「樒(しきみ)」をお供えする
浄土真宗では、通常のお仏壇に供える水やお茶はお供えしません。
「浄土には八功徳水(はっくどくすい)という清らかな水で溢れていて、喉が渇かない」といった理由から、水をお供えする必要がないと考えるためです。
代わりに「樒(しきみ)」という葉を、華瓶(けびょう)という小さな花立に挿してお供えします。
樒は毒性が強く、邪気を払うお清めの力があるとされているからです。
葉を水に挿すことで、清らかな水(八功徳水)に見立て、極楽浄土の世界を表す意味合いもあります。
西本願寺派と東本願寺派の仏花や仏壇マナーの違い
浄土真宗の西本願寺派(本願寺派)と東本願寺派(真宗大谷派)では、仏花をはじめとしたお供え物が大きく異なります。
まず、お仏壇に関わるものについて、東西の違いを確認しましょう。
お仏壇まわりの東西の違い
| 西本願寺派 | 東本願寺派 | |
| お仏壇 | 柱が金箔 | 柱が黒塗り |
| 仏具 | 黒色のもの | 金色のもの |
| 飲食 | 山形に盛り付け、蓮の「花」を表現する | 円柱に盛り付け、蓮の「実」を表現する |
| ロウソク立て | 銅に漆塗りをした宣徳製のもの | 亀の上に鶴が乗った「鶴亀火立」と呼ばれる形のもの |
また、お経の読み方や数珠の持ち方などにも違いがあります。
お客や数珠などに関する東西の違い
| 西本願寺派 | 東本願寺派 | |
| 「南無阿弥陀仏」の読み方 | なもあみだぶつ | なむあみだぶつ |
| 数珠 | 房を下に垂らし、上部を親指で押さえる | 房を上にして、左手側に垂れるように持つ |
上記のように、お仏壇周りにもさまざまな違いがあるので、これから仏花や仏具を用意する方は注意しましょう。
\16時までのご注文で当日発送/
仏花・仏具の基本配置3パターン(三具足・四具足・五具足)
仏花・仏具の数や配置には、いくつかのパターンがあります。
浄土真宗の場合は「三具足」「四具足」「五具足」という3つのパターンがあり、それぞれ意味合いが異なるので注意が必要です。
なお、通常の前卓に置くのは三具足か五具足のみで、四具足は大型仏壇の上卓(うわじょく)という別の場所に用います。
以下の項目で、それぞれのパターンについて解説しますので、どんな場面でどのように配置するかを把握しておきましょう。
三具足(さんぐそく)は普段使いの仏具一式
三具足(さんぐそく・みつぐそく)は、最もシンプルな仏具の組み合わせです。
三具足で用意する仏具
| 仏具 | 個数 |
| 花立 | 1個 |
| 香炉 | 1個 |
| 灯立(ロウソク立て) | 1個 |
三具足は、故人を自宅で安置する際に用意する「枕飾り」や、普段の仏壇に揃えるものとして広く用いられています。
四具足(しぐそく)は主に浄土真宗系で使われる
四具足(しぐそく)は、浄土真宗系で用いられる仏具の組み合わせです。
大きな仏壇で「上卓(うわじょく)」が置ける場合にのみ使います。
例えば、上卓には四具足、前卓に三具足といったかたちで仏具を用意します。
四具足は、西本願寺派と東本願寺派で揃えるものが異なるので注意しましょう。
四具足で用意する仏具
| 仏具 | 個数 |
| 華瓶・仏飯器 | 2個(一対) |
| 香炉 | 1個 |
| 灯立(ロウソク立て) | 1個 |
大きな違いは、華瓶と仏飯器どちらを置くのかという点です。
西本願寺派では、華瓶2つを一対となるように設置します。
一方、東本願寺派(真宗大谷派)は仏飯器2つを一対となるよう飾るのが基本です。
宗派ごとの違いをふまえて、適した仏具を用意しましょう。
五具足(ごぐそく)は葬儀や法事向け
五具足は、葬儀や法事といった大切な場面における仏具の組み合わせです。
五具足で用意する仏具
| 仏具 | 個数 |
| 花立 | 2個(一対) |
| 香炉 | 1個 |
| 灯立(ロウソク立て) | 1個 |
香炉を挟むようにして、内側に灯立、外側に花立を設置します。
浄土真宗においては、開祖の命日である「報恩講(ほうおんこう)」や、祥月年忌法要、御遷仏法要といった特別な場面でのみ五具足を用います。
\16時までのご注文で当日発送/
浄土真宗での仏花の生け方と仏壇への飾り方のマナー
 浄土真宗での仏花の生け方や、仏壇への飾り方にはいくつかのマナーが存在します。
浄土真宗での仏花の生け方や、仏壇への飾り方にはいくつかのマナーが存在します。
細かいルールに感じるかもしれませんが、それぞれ意味があるので、しっかりと把握しておきましょう。
以下では、仏花の生け方や仏壇への飾り方に関するマナーを4つ紹介します。
① 仏花の花は奇数本用意する
仏花は奇数(3・5・7・9本)で構成しましょう。
花立が2つある仏壇であれば、どちらも同じ本数で揃えるようにしてください。
奇数にする理由は、中国において割り切れない数は縁起が良いとされているからと言われています。(諸説あります)
また、親族が割り切られず、長く縁が続いていくようにといった願いが込められているからとも言われています。
奇数であれば何本でも問題ないので、仏壇のサイズに合わせて選んでください。
② ひし形になるように生ける
仏花はひし形になるよう、バランスよく生けていきます。
最も長さのある花を頂点に、そして段々とボリュームのある花へと移行し、最下段にはコンパクトなお花を用います。
ひし形にするのは、仏教で用いられる「榊(さかき)」を表現するためです。
榊は、神の世界と人間界との境にある木、または栄える木といった意味が由来だとされています。
こうした縁起の良い榊の形状を模して、仏花もひし形に生けるようにしましょう。
③ 仏花の表側がお参りする人の方を向くように置く
お花を花立に生けたら、お参りする側にお花が向くように調整しましょう。
至近距離だと分かりにくいので、仏壇から少し離れて確認するのがおすすめです。
また、ロウソク立てや花立の位置も、左右対称となるようしっかり調整します。
ロウソクに近い葉があれば、カットするか距離を離すようにしてください。
仏壇全体がバランスよく見えれば、仏花の完成です。
④ 五具足の場合は一対に配置する
五具足の場合は、左右対称の一対となるように配置しましょう。
向きは三具足と同様に、お参りする人のほうを向くよう調整します。
仏花を生けた後は、水を毎日交換して、きれいな状態を長く保てるようにしましょう。
必要に応じて延命剤を入れておくと、お花が長持ちしやすくなります。
仏花が枯れてきたと感じたら、仏具を掃除して新たな花を生けるようにしてください。
\16時までのご注文で当日発送/
初心者向け|仏花の仏壇への生け方と飾り方
 仏花を仏壇に供える際、どうやってやれば良いのか不安を抱く方も少なくありません。
仏花を仏壇に供える際、どうやってやれば良いのか不安を抱く方も少なくありません。
しかし、最低限のルールさえしっかりとおさえれば、適切なお花をきれいにお供えできます。
以下では、初心者の方でも簡単に仏花を生けられる方法を6つのステップで紹介しますので、ご覧になりならが仏花を用意してみてください。
① 「三具足」「五具足」のどちらにするか決める
まずは、三具足・四具足・五具足のどのセットにするかを選びます。
三具足であれば花立は1つ、五具足であれば2つ用意するのが基本です。
改めて、各組み合わせの意味を確認しておきましょう。
三具足・四具足・五具足を用いる場面
| 組み合わせ | 用いる場面 |
| 三具足 | 枕飾り、または通常の仏壇に用いる |
| 四具足 | 大型仏壇の上卓に用いる |
| 五具足 | 葬儀や法事などの節目となる場面で用いる |
四具足は、上卓がある場合に用意します。
四具足と三具足の組み合わせであっても、花立は1つです。
洋風な住宅に合うデザインの「モダン仏壇」やコンパクトな仏壇であれば、三具足の形式で準備して問題ありません。
② 必要なもの(仏具や道具)を用意する
どの具足にするかを決めたら、仏具を用意しましょう。
それぞれの具足で必要になる仏具は以下のとおりです。
それぞれの具足で必要になる仏具
| 組み合わせ | 用いる場面 |
| 三具足 | 花立×1、香炉×1、灯立(ロウソク立て)×1 |
| 四具足 | 華瓶・仏飯器×2、香炉×1、灯立(ロウソク立て)×1 |
| 五具足 | 花立×2、香炉×1、灯立(ロウソク立て)×2 |
今後「五具足」を用意する可能性がある場合は、まず五具足のセットを購入して、適宜仏具を減らすようにしましょう。
③ 仏花を奇数本用意する
具足が決まったら、花立の個数に応じてお花を奇数本用意していきます。
ただし、奇数本であればどんなお花でも良いわけではありません。
浄土真宗では「タブーな花」の特徴がいくつかありますので、注意が必要です。
浄土真宗の仏花におけるタブーなお花
| 組み合わせ | 用いる場面 |
| トゲのある花 | 人を傷つけるため |
| 毒のある花 | 人に危害を加えるため |
| 臭い匂いがする花 | 美しい浄土にはないため |
| ドライフラワー | 殺生を連想させるため |
| 枯れている・枯れかかっている花 | 死を連想させるため |
| 痛みやすい花 | 枯れやすく供え物に適さないため |
| 縁起がよくないとされる花 | 椿・アサガオなど、供え物に適さないため |
| 生花以外の花 | 香りがない、仏様の慈悲を表すのに適さないため |
| 季節に合わない花 | 仏様に供えるのに適さないため |
仏壇は、仏様のいる浄土を表したものです。
そのため、清らかな浄土にないであろうお花は基本的に仏花として使えません。
また、供え物として適さないお花や、殺生・死を連想させるお花も避けましょう。
浄土真宗の仏花としてふさわしお花の色と種類
| 色 | 種類 |
| 白 | トルコキキョウ・白菊・ユリ・胡蝶蘭 |
| 黄 | キク・キンセンカ |
| 紫 | リンドウ・スターチス・トルコキキョウ・アイリス |
| 赤 | カーネーション・ケイトウ・ほおずき |
| 桃(ピンク) | アンスリウム・ミソハギ・グラジオラス |
色に関しては「白・黄色・紫・赤・桃(ピンク)」の5色、もしくは「白・黄・紫」の3色が基本です。
上記のようにさまざまなルールがあるため、仏花選びには細心の注意を払いましょう。
なお、HanaPrimeでは仏花に最適なお花を各種取りそろえています。
本数やマナーにあったお花を取りそろえていますので、仏花にお悩みの方はぜひHanaPrime公式サイトをご覧ください。
④ お花を水切り・茎切りする
お花を長持ちさせる手法として「水切り」があります。
茎を水に浸しながらカットして、新鮮な水をたくさん吸収させておく方法です。
水切りする際は、新鮮な水を用いること、切りやすいハサミで1〜2cmほどを斜めにカットすることを意識すると、うまくできます。
お花の長さは、花立の3倍ほど、もしくはロウソクと同じくらいの高さにするのがよいとされています。
厳密なルールはないので、きれいに見えるかたちでカットしましょう。
⑤ 長い花(樒や菊)から順番に花立てに生ける
仏花を花立てに生ける際は、以下のステップで生けてみましょう。
- ステップ①樒(しきみ)をロウソクと同じくらいにカット(もしくは花立の三倍程度の長さにカット)
- ステップ②大きく外れている葉があればカット
- ステップ③リンドウや大菊のように長く直線的なお花を重ねる
- ステップ④段々と低く、かつ濃い色になるように、ほかのお花を重ねていく(ボリュームのあるお花を中盤にして、ひし形になるよう調整)
ただし、これらはあくまで綺麗に見えるための条件であって、ルールではありません。
花の状態や色合いなどを見ながら、バランスよく見えるよう工夫していきましょう。
仏花が完成したら、必要に応じて輪ゴムでまとめ、茎をカットします。
切り口が斜めになるよう整えると、お花が長持ちするのでおすすめです。
⑥ 花立を仏壇に飾る
仏花ができあがったら、花立に飾り付けましょう。
花立にお花を生けたら、お参りする側にお花が向くように調整します。
至近距離だと分かりにくいので、仏壇から少し離れて確認するのがおすすめです。
また、ロウソク立てや花立の位置も、左右対称となるようしっかり調整します。
ロウソクに近い葉があれば、カットするか距離を離すようにしてください。
仏壇全体がバランスよく見えれば、仏花の完成です。
\16時までのご注文で当日発送/
浄土真宗の仏花と仏壇についてよくある質問
浄土真宗の仏花や仏壇をお持ちの方は、扱いやお花の選定などに悩む場面が多くあるかと思います。
特に、どんな花を選べば良いのか、節目の場面で何か注意点があるのかといった部分で、疑問を感じる方が多いでしょう。
以下では、浄土真宗の仏花と仏壇に関するよくある質問6つに回答していきます。
浄土真宗の仏花に生花以外を飾ってもいい?
浄土真宗においては、できる限り生花を用いるべきとされています。
仏花は、香りを含めてお供えする、また死を持って諸行無常を表す「仏様の慈悲」を表現するといった意味合いがあるためです。
ただし、どうしても生花を飾るのが難しければ、プリザーブドフラワーや造花などドライフラワー以外のものであれば飾ってもよいとするケースがあります。
ドライフラワーは、お花を乾燥させる製造方法から、殺生や死を連想させるため、使用できません。
生花を用意するのが難しくても、法要やお盆といった節目のタイミングは生花を供えるようにしてください。
浄土真宗の仏壇に飾る「葉っぱ」の名前は?
浄土真宗の仏壇に飾る葉っぱは、主に「樒(しきみ)」と呼ばれる種類を使っています。
樒は日本・中国・韓国に生息するマツブサ科シキミ属の植物です。
香りが良いためお香の代わりとして用いられることもあり「仏前草」と呼ばれ親しまれてきました。
なお、他宗派ではサカキ・ヒサカキ・荒神などを供える場合もありますが、これらは毒性がないため、浄土真宗では樒を供えるのが好ましいでしょう。
浄土真宗の49日法要における仏花の飾り方は?
浄土真宗の49日法要では、白を基調とした仏花を飾ります。
具体的には、キク・ユリ・胡蝶蘭などを用いるのが一般的です。
白以外を用いる場合もありますが、薄いピンクやクリーム色など、なるべく淡い色のお花を使うようにしてください。
華やかな色、特に赤は祝い事を連想させてしまうためNGです。
仏花は毎日替えるべき?
仏花は毎日替えなくても問題ありません。
様子をみて、枯れてきたと感じたら別のお花を生けるようにしましょう。
ただし、花立のお水は毎日替えるようにしてください。
水を放置するとバクテリアが繁殖し花が痛みやすくなります。
通常の水道水であれば毎日、延命剤を入れたお水は数日おきに交換してください。
なお、HanaPrimeでは花もちがよいお花をご用意しております。
お花の定期便サービスもありますので、ぜひご利用ください。
仏壇が狭くて具足を飾れない場合はどうする?
モダン仏壇やミニ仏壇で、具足を飾りきれない場合は、略式で仏具を飾ります。
まず、ご三尊の前に「仏器膳(ぶっきぜん)」を置いて、そのうえに「仏飯器」と「湯茶器」を、両側に「高杯」を飾ります。
一段下(中断)には、左側に「花立」を、右側に「過去帳」を設置しましょう。
そして最下段には、左から「線香差」「マッチ消し」「香炉」「ローソク立て」「リン(リン棒)」「見台」を、花立と過去帳の間に収まるように設置します。
中段がない場合は、下段で前後に分けるようにして飾るのが一般的です。
浄土真宗の仏花は東西本願寺のルールに合わせて飾りましょう
 仏花には、避けるべきとされるものがいくつもあります。
仏花には、避けるべきとされるものがいくつもあります。
面倒に感じるかもしれませんが、仏様や故人に供えるお花なので、心を込めて選びましょう。
丁寧に生けられたお花は、仏様だけでなく自分自身にとっても心地よいものとなります。
しかし、月に何度もお花を生け替えるのは大変と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな仏花の管理にお困りの方には、お花の通販サービスHanaPrimeがおすすめです。
直接契約している国内の提携農園から、直接仕入れを行っているため、高品質なお花を低価格でご提供しています。
配送前に商品の写真を確認できるので、品質に不安がある方にもぴったりです。
仏花はもちろん、自宅用のお花も各種取りそろえておりますので、興味のある方はぜひ公式サイトをご覧ください。
胡蝶蘭、スタンド花、花束、アレンジメント、観葉植物などフラワーギフト全般を取り扱っています。


株式会社HanaPrime/メディアチーム
株式会社HanaPrime